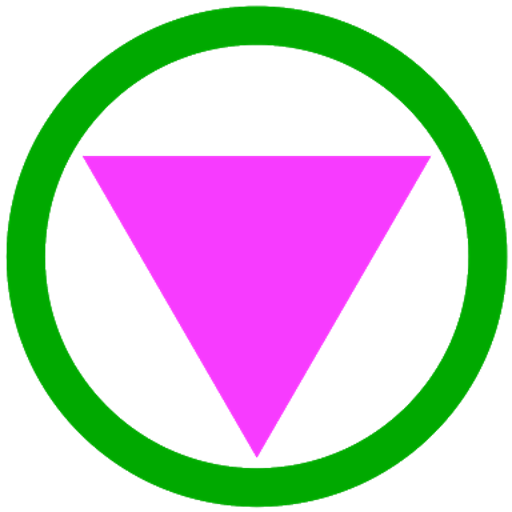人間の才能について最近考えること
眼差しという才能
性質ともまた違う、もっと潜在的かつ根本的な領域で、天才的な眼差しを持つ人間がいる。上辺に踊らされることなく、本質を見抜こうとするその鋭さは正に才能と言える。最近そういった才能を持つ人々の強さをまざまざと見せつけられることがあって、非常に感銘を受けた。彼らに物事はどう見えているのだろう。僕は飽きっぽく専門性を高められない人間であるから、どうにかして彼らの才能を盗みたいと常々考えている。しかしなかなか難しい。ふとした瞬間に甘えのようなものが出てしまって、充分に真理を探究出来ない。正しくは、その努力を継続することが出来ない。僕は、意識して努力しないとその眼差しを持つことが出来ない。
歳をとり、人の才能に嫉妬をすることが減った。嫉妬する前に尊敬してしまうようになった。これはこれで善い変化にも思えるが、対抗心というか、強いエネルギーをもって彼らと対等以上の眼差しを持ち続けようという意志が揺らいでしまう。諦念をつらつらと書くのもあまりにデカダン過ぎるか。しかしまあ、若い才能や若さという資質にはどこか眩しさを感じるようになってしまったのは事実だ。羨ましいとも妬ましいとも思わない。ただただ感嘆してしまう。失いたくないものだ、若さというものは。
努力を継続する才能
元々の能力、成長速度に驕らず努力を継続できる人間がいる。これもまた相当な才能だと言える。そして僕が持ち得なかった才能だ。最終的に勝つのはこういう人だ。驕らず努力を続け、気がつけば誰よりも専門性や信頼を獲得している。少しずつの積み上げを苦に思わず、堅実に信用残高と能力を身につけていく。素晴らしい。僕が一番欲しかったのはこの才能だ。そして僕が凄まじく遠い距離を自覚しているのもこの才能に対してだ。
四半世紀以上生きてきたことによって、一瞬の辛さにはある程度耐性が出来た。しかし継続的な苦しみにはまだ弱い。とくにエンジニアという職種においては、日々進化していく技術を追わなければならない。考えれば途方も無い話だ。常に新しいものをキャッチアップしていかなければならないわけであるが、しかし確かにそれが出来る人間は一定数いるのだ。先程僕は歳をとり、妬みや羨みを持たなくなったと言ったが、僕はこの才能を持つ人に対しのみ未だ劣等感を覚える。客観的に捉えて、明らかに彼らの方が優れた人間だと僕の眼差しは語っている。
素直さという才能
自分が分からないことを素直に認めることは非常に難しい。自分に非があるなんて考えたくもない。歳をとるということはそういうことだ。人間は元来嘘をつき誤魔化す能力に非常に長けている。残念ながらそれが役に立つシーンも確かにあるのだが、基本的にそれは素直さという才能に勝てることはない。素直でいられる人は自然と周囲の人間に助けられ、人を助ける。何事も真摯に受け止め吸収する。そしてまたそれが同時に人々を助けることになる。他人を巻き込み、他人から吸い上げ他人に還元する。理想的なサイクルだ。
僕が自分から最も遠い才能であると感じるのがこの素直さという資質だ。もはや距離がありすぎてそうなりたいとも思えない。自分が少しも近付けないからこそ、本当に心から尊敬できる。
たまたま今所属している組織にはこの才能を持った人が多く、その点で言えば僕は非常に恵まれている。彼らは常に自らを省み、人の意見を素直に受け止める。本人はただがむしゃらにか自然にか生きているだけなのかもしれないが、僕のような上辺だけではない本当の意味での他人に対する尊敬、自身に対する謙虚さを忘れずにいられる人間はまさしく彼らしかいない。彼らとは非常に付き合いやすく、共にいるととてもいいことがある。なんだか、彼らの放つ眩いばかりの光は僕さえも明るく照らし、僕の抱える醜い部分を消し去ってくれるような感覚がある。
人の上に立つ者がどうあるべきなのかは僕にはわからない。しかし、僕は少なくとも共に歩くのならば素直な人がいい。
魅せ方という才能
世の中には、自分の魅せ方が極端に上手い人がいる。他人からどう映るか、どうすれば自分に利のある見え方をするか、彼らは自然にその観点を持ち続けられる。刹那主義かつ快楽主義の極みのような人間である僕には、当然ながらこの才能もない。やることはやっていても、すごいことをやっていても、それを巧く魅せることができない。普通の仕事を普通にこなしているだけなのだが、何故か根拠もなく信頼したくなる人はいる。
キャラクターというよりは、セルフプロデュースに関する才能なのだろう。この才能を持つ人が困っていると、無性に手を差し伸べたくなる。堪え性のない僕なんかは、いくらいけ好かない相手でもすぐに助けようとしてしまう。弱みの魅せ方まで彼らはうまいのだ。計算づくだとしても素晴らしい。この才能だけは唯一自分になくてよかったと思う才能だ。思うに、僕は魅せ方が下手だからこそ平凡にまで成り上がれた。この才能があったなら、僕は無能も無能、何も出来ないくせに口だけ達者な奴になってしまっていただろう。
楽しめるという才能
何をやるにしても楽しめる人間がいる。信じられないが、確かにそんな奴がいる。何か異常な神経伝達物質が脳内に充満しているのではないかと疑ってしまうくらいの奴だ。彼らは果たして本当に僕と同じ種族の生き物なんだろうか。何をやっても楽しいならば、きっと彼らは何にでもなれる。好きこそ物の上手なれという格言があるけれども、ならば彼らは全知全能になり得る存在とまで言えるかもしれない。
働くのが楽しいという人に、思い切って聞いてみたことがある。何がそんなに楽しいのか、家にいる方が楽だし疲れないんじゃないかと。すると彼はこういった。
会社で仲のいい奴と集まれるってだけで楽しくないか?
僕には全く同意できない発言だった。例えば家に帰るのが嫌な理由があるとか多動的な性質があってじっとしていられない等の話なら理解出来なくはないが、彼の場合はそうではなさそうだった。もう全くもって意味不明だ。人生を美しいとか、生きてるだけでいいことだとかいう人はもしかするとみんなこの才能を持っているのかもしれない。少しの理解も共感も出来ないが、生物として最も優れた才能はこの才能だと感じる。
非才を自覚する才能
僕が唯一持ち得た才能はこれだ。僕にはどうやら上に挙げたような才能はない。彼らと同じ空の下で同じように生きているはずなのに、僕はやはり彼らのようには生きられない。
勘違いしないでほしいのは、これを悪いことだと考えているわけではない。諦めが肝心なんてよく言うけれど、僕はそこに関しては非凡な才能を発揮できるというわけだ。
自分は天才だ、やれば出来る子だ、と思い続けてきた四半世紀。それは長い年月だった。しかし僕はこの才能故にその莫大な時間の威力を凌駕する熱量で、自分を諦めることができたのだ。この点について、僕は自分の才能に感謝の念を覚えている。
過去の自分と今の自分を振り返って
恐らく、前職の同僚達は僕の能力を低く感じていただろう。彼らの意見は一方では正しい。みんながそれぞれ持っている上で列挙したような才能がぼくには欠落していたから、そう見えても仕方がない。
みっともないようだけれども、僕はもう人になんと言われようが誰にどう見られようが本当にどうでもよくなってしまった。自分が明日生きていようが死んでいようが本当にどうでもいいのだ。世間体とか、お金とか、生きる意味とか、全部が全部どうでもいいのだ。今はまさしく慣性の法則に従順に、ただただ日々をこなしている最中であるし、恐らくこれからもきっとそうしていくのだろう。他人に叱られても嫌われても何も思わない。仕事上の建設的な話は半ば無我の境地というような感じではあるが真摯に聴く。一生懸命という程は決して頑張れないけれども、それなりの質でにそれなりのことをそれなりの速度でそれなりにやれる。それが僕の今のところだ。
しかし一方で、それでもどこか心の中に自身の才能を見つけ出したいという無自覚の欲求があり、ぼくの心は未だ無知の知と呼べるほど成熟はしていない。この厚かましい感情は不思議なものだ。救えないのは、先述したような才能のある人間、または成熟した人間になりたいというわけでもないところである。このままの僕で出来ること、なれるポジションのようなものを模索しなければならない。何かいいアイディアがあったら教えてくれ。
雑談の重要性 - 雑談が無駄だという迷信
雑談すると仕事が始まる説
あくまで個人の見解だが、世の中のチームの半分以上は雑談が足りていないチームだと思う。現代においても未だ雑談ばかりしていると「サボっている」と周囲から認識されてしまうのは事実だし、確かにそればっかりしているのはよくない。しかし、私語を慎め、という規律が正義とされるのも如何なものかと最近感じる。
雑談が持つ力というか、雑談する時間を確保するということがもたらすメリットも多大にある。共に仕事をしている人は当然として、普段あまり業務上の関わりを持たない人と話すこともとても大切だ。
共に仕事をしている人のことはなるべく知っている方がよい。プライバシーの問題もあるから出身地や年齢、家族構成、趣味、パートナーの有無をどこまで知るべきとは明言できない。しかしその人なりのキャラというかカラーというか、どんな時に何を考える人なのか、ということをせめて想像くらいは出来るようになっておくべきだ。
雑談から仕事が始まることもある。というかエレベーターピッチなんてのも雑談と自己紹介の間みたいなものだし、そんなに珍しいことでもないだろう。例えば僕の場合、今考えていることを言葉や文章にして発したいという欲求の赴くがまま、あまり知らない先輩や同僚に話しかけたりチャットを送ったりすることがある。すると大抵、"なぜ自分に?"という疑問を抱えながらも相手なりの見解を返してくれたりする。中には実は自分も興味ある領域なんだよね、面白そうだから企画にしてみようと話が持ち上がったりすることもある。
ついこの間コミュニケーションの難しさについて記事を書いたが、無計画で無遠慮、無鉄砲なコミュニケーションというのも時には役に立つのだ。
悪気はなくとも、言葉は人を傷つける。 - ここはクソみたいなインターネッツですね
僕は初対面の人に嫌われることが多いので、普段はあまり突拍子なことはしないようにしている。けれどもやはり、感情の昂りや無意識的な手癖のようなもので時折そういったことをしてしまう。少し冷静になった際に「なんでこの人に急に話しかけてしまったんだろう」と自責の念を感じることもあるが、しかし結果的にはいいことが起こった経験の方が多い。自分以外の人は自分より優秀なのだから、そんなことは当たり前とも言えるが。
特に自分より、その時々の意味で経験豊富な人に話しかけるとよい。なぜなら経験豊富で達人的な人は大抵余裕があり、一見下らなそうなことでも真摯に話を聞いてくれるからだ。そして、そういった人たちを選ぶことで自分へのプレッシャーも与えられる。そんな親切な人たちの時間を無駄にしないよう、なにか建設的な着地点を見つけようと努力をして思考するようになるのだ。達人達は僕の「こんなことを思っている」という一方的な表明を、コミュニケーションを通して「それは根本的にはこういう問題なんじゃないか」と課題の見える化を補助してくれる。課題の輪郭が明確に見えているならば、あとはそれを解決できるようなアプローチ方法と誰の力が必要かを考え行動に移すだけだ。僕は実際、こんな風に自分に仕事を与えていることが多い。
そんなことを繰り返していると、気がつけば周りに相談ができる相手が増えている。特に課題を発見するためのコミュニケーションを手伝ってくれた人なんかは、課題を一緒になって発見した、という当事者意識があるので進んで協力してくれるようになる。そして、こんな問題があるのであなたの力が必要なのです、とお願いされて悪い気がする人は少ない。尊敬と信頼を込めてしっかりとお願いすれば、相手もまたそれを返してくれるものだ。
こんな風に、僕は人に頼ることで仕事を円滑に進めることを推進している。またその入り口として雑談というものが重要になり得ることも主張したい。
雑談の必要性と難しさ
では全てのチームが雑談をする時間を設けるべきかというとそうではない。熟練したチームにおいては、そのような時間を設けずとも必要があれば自走的に雑談をするだろうし、相互理解が充分に進んでいるのなら雑談を通さなくても課題を共通認識として持つことも可能である。既に理想的なチーム構築が出来ており、雑談をあえてする必要がないというチームもあるわけだ。
また、雑談がうまく機能しない場合もある。例えばマイクロマネジメントやパワーマネジメントを採用しているチームにおいて、雑談は雑談でなくなることが多い。当初は雑談の場として時間を設けたにもかかわらず、普段の関係性から報告/連絡/フィードバックの場に変化してしまう。マネジメントとは部下の行動や思想を全て掌握することではない。部下を理解/信頼し、自身やチームの成長を促進することを言う。相互理解を進め、一定の権限を委譲し、問題となりそうな点をあらかじめ排除し、それでも起きた問題の責任は自分が取ると明言し、相互に信頼関係を構築することがマネジメントの第一歩だ。トップダウンで思い通りに部下を動かすことを至上とするチームでは、雑談を充分に作用させることは難しく、恐らくは誰にとっても無駄な時間になるだろう。
そして、この雑談の場というのはなかなか下から発信して設置するのは難しい場合が多い。声の大きい人は「ちょっとお話があるんですが」の一言を発することに対する抵抗がないかもしれない。実際僕は声が大きい方なので何も気にせずそのようなことができる。しかしやはり声の小さい人はどうしても「雑談など持ちかけては貴重な時間を無駄にさせてしまうのではないか」というプレッシャーを感じてしまい、なかなか言い出せないものだ。
であるからこそ、自分のチームに雑談が必要かどうか、マネジメントを担っている人間が日々チームメンバーの観察をしながら判断すべきなのだ。その際気をつけて欲しいのは、雑談にアジェンダはいらないこと。雑談の場に力関係を存在させてはならないこと。まずは相手の話を傾聴すること。相手を否定しないこと。遠慮や忖度をさせないこと。雑談は必ずしも仕事に繋がるとは限らないこと。それでも必要な雑談があると認識すること。
以上、私見でした。
プログラミング講師が考える、プログラミング学習に必要な資質と講師側の規範、また教育というものについて
真新しいスーツに身を包む方々が目立つ季節となりました。私の下にも新卒の方が2名程つくことが決まり、久しぶりにできる後輩というものへの接し方に関する不安、彼らを一人前に育て上げなければならないという責任の重さから、柄にもなく非常に緊張しています。しかしこれは良い機会であると前向きに捉え、このタイミングで今一度後輩や教育というものに関する私の考えをまとめておきたいと思います。
まずはじめに自己紹介をしておくと、私はCODED@というプログラミング講座団体を立ち上げ、講師としてプログラミング講座を実施しております。
私たちの講座は二日間の短期的な講座であることが特徴です。webサービスの基本的な動き方の説明から、実際にハンズオンでapache,PHP,MySQL,HTMLを利用してtodoリストを動かしてみるところまで体験ができます。プログラミング未経験者、初学者をメインターゲットとしております。実績として、就活生向けのイベントやIT企業の内定者研修として実施させて頂いております。
企業様や様々な方のご協力のおかげで、今では受講生はのべ50人以上にもなり、それなりに知見やデータが溜まってまいりました。二日間という極僅かな時間にもかかわらず、プログラミング能力やプログラム的思考能力が伸びる方となかなか伸び悩む方というのがだんだんとみえて参りました。
今回は私なりに感じたプログラミングに必要な資質と、プログラミングを教える際の注意点をいくつかまとめておきたいと思います。尚、現在も所属している企業で内定者研修を行っている最中です。
プログラミング学習に必要な資質
教育による成長というものは、教える側教わる側双方の要素が複雑に絡み合っているものです。本章では受講者側にフォーカスしていきたいと思います。
些か乱暴な分け方かとは思いますが、私の経験から伸びる受講生と伸び悩む受講生の間にある違いについて大きく分類します。
- 意欲と目的
- 好奇心の豊富さ
- 献身の精神
- 楽しめるかどうか
1. 意欲と目的
いきなり身もふたもない話ですが、やはり意欲のある受講生とそうでない受講生では差が生まれます。意欲とは何か、というと「習得したい」という思いです。私の団体は基本的には受講希望者を募って講座を実施しています。つまり積極的に参加して下さる方が集まっていると言えます。にも関わらず、受講生の意欲には差があります。昨今、世の中ではBTC人材というビジネス、テクノロジー、クリエティブ分野に横断的な知識を持つ人材が求められていますが、やはりそのような人材をを育てる、あるいはそのような人材になる、ということは非常に難しいことです。
何より、未経験からプログラミングを学びたいという方は大抵「一般常識としてちょっと触ってみたい」、「なんとなくやった方がいい気がする」というふんわりとした動機から受講されます。確かに現代社会においてITリテラシーは必要ですし、役に立つ場面も多いことでしょう。しかしやはり、何のために技術を学ぶのかという目的を明確に持っている人とそうでない人では食らいつく力が違います。
強い意欲と目的意識のある受講生には様々な方がいました。目的もそれぞれ違っていて、とても興味深いのです。エンジニアになりたい、作りたいサービスがある、入りたい会社がある、ハッカーに強い憧れがあるなど分かりやすい目的に始まり、就活に失敗したのでスキルを付けなければ生きる術がないと考えていた方、家業のIT化や効率化を推進することで実績を得て、お兄さんから家督の座を奪いたいという方など、中々差し迫った事情をお持ちの方もいらっしゃいました。
私は精神論や根性論はあまり好きではないのですが、意欲というものはその維持が可能な限り大変に人間の才能を伸ばす要素であることは間違いありません。そして、意欲というものは明確な目的があってこそ生まれるものであるということもまた間違いないことでしょう。しかし私の努力不足故に申し訳ないところではありますが、残念ながら、やる気がある方が必ずしも伸びるというわけではありませんでした。そちらは次の要素に関わるお話です。
2. 好奇心の豊富さ
知的好奇心の強い方というのは、凄いです。3を教えるだけで10以上のことを自走的に学びます。彼らに言わせれば「じゃあこうしたらどうなるんだろう?」という問いを立てて実践することでより理解が深まり、達成感を感じるそうです。
私なんかは学生時代はまともに勉強をしておりませんでしたが、きっと彼らはそうやってずっと勉学に励んできたのでしょう。やらされているのではなく、自分で仮説立てから検証までを自発的に行うのです。私たちの講座では練習問題を用意してあるのですが、彼らはより発展的な応用問題を自身で作り、それに挑戦しようとします。そして、詰まっても決して答えを訊こうとはしないのです。ここからここまでは理解できていて、ここでどのような技法を用いればいいのかだけがわからない。それをそのまま教えるのではなく、ヒントをくれと要求してくるのです。メンティとしての才能がそもそもあるのです。
こういった受講者には、敢えてあまり手をかけないようにしています。日本の教育による悪影響なのかどうかは分かりませんが、彼らは我々に干渉されることを嫌います。自身がおかしな仮説を立てているかもしれないから見られるのが恥ずかしいとか、勝手に進むことはいけないことというふうに考えているのでしょうか。
何にせよ、意欲や目的はさほど明確でないのに、自由にやらせておくだけで勝手に成長していく受講生も一定数いるのです。これは一種の才能であると私は思います。誤解のないように申し上げておきますが、これはプログラミングにおいて才能が必要であるという話ではありません。学習という領域において、メンティとしての才能、言い換えるならば衝動とさえいえる彼らの好奇心は大変に有効な才能であり、おそらく彼らはどんな分野の学習でもその才能を発揮できるでしょう。
3. 献身の精神
また、5,6人以上の受講生に教えていると大抵1人は献身的な学習方法を取る方が居ます。周りの遅れている方を率先的にフォローし、フォローをするリソースを空けるために先の単元をどんどん吸収していく方です。私たちもなるべく噛み砕いた説明を用意するよう心掛けているのですが、私たちが気付かないようなところに引っかかってしまう方がいたりします。献身的な方は、そうした人々を助け、また本人も人に教えることで知識の定着を得ていきます。人に教えるという方法は非常に有効な学習方法です。言語化することで知識は整理され、教えていく中で不足している知識が明確になり、次に何を掘り下げるべきなのか、と自身の状況を俯瞰できるようになる上に、その知識が必要とされる背景、文脈を捉えてから学習をするという非常に理想的な知識の定着フローを自然と踏めるようになるのです。
こうした学習方法を自然にとれる受講生がいると、私たちとしては教えるのが非常に楽です。しかし一方で、このような方はその当人しか伸びず、他者の成長を阻害してしまうという事態を起こす危険を孕んでいます。
このような学習方法を取れる方が他の受講生に教えること自体は献身的で素晴らしいことです。しかしその当人がメンターとしての行動指針をしっかりと確立しているとは限りません。私たちの講座ではメンタリングとティーチングを織り交ぜています。必要な知識を与え、そこから先はなるべく受講生の主体性を引き出し講座の着地点を変化させていく手法を取っています。その方針のなかで、他の受講生に対し親切心からすぐに答えを教えてしまう受講生がいると、他の受講生に「考えさせる」という重要なタームを経験させることができなくなってしまいます。
これは後述致しますが、場をうまくコントロールして、受講生全員が主体的に学び、また偏りなく補い教え合うような環境を作り出すということが私たちの課題となります。これはとても難しいことです。そして、私たちにとって、常に改善を怠ってはいけない重要な価値のコアになる部分でもあります。
4. 楽しめるかどうか
以上全ての特徴を集約する大前提として、「楽しめるかどうか」という要素は重要です。また、上述したように人によって楽しさを感じる観点は違います。プログラミング自体を楽しいと感じる方や、新しい知識を得ること自体にポジティブな姿勢を保てる方、出来ないことがだんだんとわかっていくその達成感に楽しみを覚える方。たくさんの楽しみ方の形があります。当然、そのような楽しみ方の多様性を私たちは否定しません。理想となる楽しみ方、理想となる成長というものを押し付けるつもりは決してないのです。
受講生の方々が、それぞれの楽しみ方でプログラミング、あるいは大きな言い方をすれば「知らないことに触れる」ということに前向きに取り組めるかどうか。それが何より重要な要素です。
講師側が気をつけなければいけないこと
先述した通り、教育(この言葉は何か上から目線のようで恐縮ですが)における成長は教育者と被教育者の相互関係の中で生まれる双方向的なものです。なればこそ、教える側である私たちは受講者の方々の意欲、楽しさ、献身を促進するような寄り添い方を強く意識しなければなりません。本章では、少ないながらも私がプログラミング講座を開いてきた中で内面化してきた教育者としての規範をいくつかお話ししたいと思います。
why、に納得感のある答えを用意する
プログラミング初学者は「なぜこれを作るのか」というところに対する納得感を得られないことで学習意欲を減退させてしまうことがよくあります。現在行なっている社内研修でも同様のことが起こりかけました。それは、function(関数)についての項目を講義している際のことです。
「プログラミングをしていると、同じ処理を繰り返し使いたくなる時があります」という説明の元でfunctionの構文や使い方について解説をしたのですが、「繰り返し使いたくなる時」という具体的状況の想像が初学者にとっては困難なのです。特に私たちが行なっている研修は二日間という短期間のパッケージであるため、可能な限り学習項目を少なく簡略化しており、確かに繰り返し使うような処理はほとんど出てきません。私の場合、実務経験に基づく例を挙げて納得して頂こうと試みているのですが、しかし十分に納得をして頂けない場合も当然ながら御座います。この点については、日々教材と紹介実例のアップデートを行い改善していかなければならないと考えています。
わからないことは罪でないことを先に断言しておく
これは当然のことですが、未経験者や初学者がプログラミングを学ぶということは、わからないことを突きつけられ続けるということです。私たちの義務は、受講者のわからなさの輪郭や原因を明確にし、理解のブレイクスルーポイントを的確に見抜き手助けをすることです。ですから、「わからない」ことに対して受講生に罪を感じさせることは愚の骨頂であるといえます。新しい領域に挑戦しようとしている人間にとって、わからないことが多いのは当然のことです。その為、自身でしっかりと考えた上でもわからないことがあれば、何度でも同じ質問をしてくださいと宣言しています。
現在、入社研修の一環として講座を開催しています。その中で、新卒の方々に「同じことを質問するな」であるとか「先輩の時間を使うことはコストである」とか、そういった思想が刷り込まれていることが少なからず見受けられます。その刷り込みは一方では正しい論理です。私もエンジニアの端くれですから、無駄なことをするのは悪であると考えています。しかし、この場合ではどうでしょうか。この講座が真の意味で無駄となるのは「受講生が何も得ず研修を終える」という状況に他なりません。つまり、この場では私のリソースを最大限活用し、貪欲に知識を得ることこそが彼らの義務なのです。私たちはこのことをしっかりと理解し、言葉遣い、表情、雰囲気作りなど様々なやりかたでこの考えを受講生と共有できるよう心掛けなければなりません。
自分で考えさせる仕組みをつくる
受講生の資質の部分でも触れましたが、知的好奇心の強い受講生は伸びやすいという経験的認識が御座います。そしてそれは当然受講生の資質だけの問題ではありません。私たちは受講生の好奇心を何らかの仕組みによって刺激し、彼らの自走性をより促進させることが可能なはずなのです。
私の場合はまたまだ試行錯誤の段階ではありますが、受講生に要件定義に関するグループワークをしてもらうタームを講座に組み込んでいます。目的は2点あります。1点目は、最終成果物を受講生に再定義させることで実際の作り方を俯瞰、想像しやすくする点。2点目は、受講生自身に成果物の開発を「自分ごと」として認識させる点です。過去の講座では、このグループワーク内で追加機能や追加要件などを出してきた受講生らが居ました。時間制限のあるなかで機能を追加することはなかなか彼らにとってハードではあったかと思います。しかし自らの意思で作ろうと決めたことで、彼らの積極性は明らかにガラッと変わりました。
その受講生たちは私が何も言わずともグループを二つに割り、分業制をとりました。チーム開発の手法を自らこの段階で生み出したという訳です。これには驚かされました。あるグループはこの機能、あるグループはこの機能、というふうに工程を分割し、統合の際はお互いに作った機能とロジックについて解説を行う。そこでロジックの正当性について議論が起こり、またより効率的な条件分岐の書き方などを共有していました。一つの理想的な開発チームがそこにはありました。この受講生らは学生でしたが、社会人ですらこのようなフローをしっかりと実践できているチームは少なく、非常に感銘を受けました。
ティーチングとメンタリングを使い分ける
短期間の講座であると、どうしてもティーチングに寄ってしまいます。しかしより効率的な学習を推進するためには、メンタリングの手法がやはり有効であると私は考えています。ティーチングとメンタリングの違いを簡単な喩えで言うと、初めて自転車に乗る子供に対する教え方の違いが相応しいでしょう。乱暴に定義しますが、自転車の乗り方を言葉で伝えあとは乗ってみれば乗れるようになるとするのがティーチングです。対して、メンタリングは子供が自転車に乗りたいというその気持ちを促進し、乗り方を自ら学び取る手助けをします。子供が転んで挫けそうになった時には「前より随分乗れているよ」と前向きな気持ちに転向させ、転ぶ恐怖を感じてしまっているならばその恐怖を取り除く等の支援をします。効率的な練習法を提示し、当人の経験と気づきを重要視するのです。
少々重複しますが、人間は自身で経験したことを基盤に成長するのです。人から教えられることや社会のセオリーから学ぶものは、確かに必要な知識として私達の中に蓄積されていきます。しかしその知識がどの程度内面化されるかというのはまた別の話です。私はその内面化の鍵は自発的な経験であると考えています。訳もわからず人に与えられた課題をこなすより、自身で論理から組み立て設定した課題を解決するほうが、より大きな達成感を得られることは自明と言えるでしょう。
この点は講師としては非常に難しいところです。あまりに受講生任せになってしまっては怠慢であるとみられてしまいます。何より、さっさと答えを教えることの方が私たちにとってはずっと簡単なことですから、時間的制約や体力の観点からそちらに流されてしまいそうになることも多々あります。しかし、私たちがプログラミング講座を開催しているのは決して私たちのためではありません。受講してくださる方の人生を、選択肢を、可能性を、私たちにできる範囲で拡張したいという理念に基づいて開催しています。ですから、私たちは自分が楽であるとか大変であるとか、そういったことを講座の場で判断軸としてはならないのです。完璧にその思いを遵守することは難しいことです。しかし私たちはその思いを念頭に置いて、常に意識と講座内容の改善を重ねていかなければなりません。人にものを教えるということは、また私たち自身も常に学び続けなければならないということです。
おわりに
長々と書いて参りましたが、受講生が伸びるかどうかの分かれ目における責任の比重は講師側に傾くと私は考えています。上に挙げたように、受講生の資質もまた重要であることに変わりはないのですが、しかし資質が一切ないと感じさせる受講生を私は1人も見たことがありません。プログラミングを楽しめるか楽しめないかという違いは確かに人によるところがありますが、一見楽しめていないように見える人でも「この方はエンジニアに向いているなあ」と思わせる閃きや論理性を表出させることがあります。そういった方が楽しめていないのは、プログラミングの楽しさを私が充分に伝えられなかったせいだと考えています。殆どの場合、彼らの責任ではなく、私の責任なのです。
人にものを教えることはとても難しいです。しかしだからこそとても面白いことでもあるのです。これから後輩を持つ方、教育に携わっている方、どうか相手を一方的に責めるのではなく、信頼、尊敬、謙虚の念を持って接して下さい。人を即座に断じてしまうことはあなたにとっても大きな損失となります。私は、そのような傲慢な姿勢をとっていたことがあり、取り返しのつかない失敗も経験しました。どうか、みなさんは私のようにならないで下さい。
新卒研修を行う上で僕が注意すること
入社半年なのに新卒研修を担当することになった
昨年12月よりエンジニアとして仕事をしている。入社から間もないにも関わらず、BTC(Business/Technology/Creative)人材育成研修のテクノロジー部分の担当として抜擢していただいた。これは僕がCODED@という学生向けプログラミング講師団体を立ち上げプログラミング講座を実施しているボランティア活動が評価されてのことだった。
プログラミング講座の方はCODED@のメンバーに了承を取り、普段実施している講座を流用することができるようになった。これはこのまま遂行できるとして、新入社員の方々とお話しできるせっかくの機会なので何か技術以外のことも伝えたい。
何を伝えるかの前に
何を伝えるか、という大きなテーマにいく前に、重要な点がある。コミュニケーションの第一歩は相手のことを知るということに始まる。つまり、一人一人の人生観、労働観、成長欲求、なりたい姿やその有無などを時間をかけてヒアリングをしなければならない。しかし今回は強い時間的制約が存在するため、そのような余裕がない。とはいえ、余裕がないからといって疎かにしていいものでもない。では翻って、僕が新卒だった時のことを思い出すことで少しでも彼らに近づいてみよう。
そもそも僕は新卒において、100%の確信を持って希望した会社に入ったという訳ではない。何をしたいのか、何ができるのか、何をすべきで何をしないべきなのか考えながら就職活動をしていたら、疲れてしまったのだ。なので真っ先に内定を出して下さったところに即決で入ることにした。もしかすると彼らもそうなのかもしれない。であるとすれば、次に僕が感じたのは「本当にここでよかったんだろうか」という漠然とした不安、「社会ってこんなものなのか」という今思えば傲慢ともいえる失望であった。空回りして自身の能力を過信してしまう時期など、多くの人が経験してきたよくある話なのだと思う。
全ての新卒が僕のように生意気であるとは限らない。しかし、彼らが漠然とした不安、言い換えるならば社会及び自身に対する期待のようなものを抱えており、それは非常な緊張と興奮による増幅に至っている可能性を頭に入れておかなければならない。一年目、というのは労働人生において大きな意味を持つとよく言われる。大筋には同意するが、僕の私見を加えるなら「一年目は思春期以来の多感な時期」であるからこそ意味を持つのではないだろうか。
人間は結論を出したがる生き物である。そして、この多感な時期には小さな出来事に大きな印象を抱きやすいきらいがある。つまり、彼らにとっての会社像、社会人像、さらに言えば大人像は研修担当によってある程度の指向づけが行われてしまいやすいのだ。このことを意識して、丁寧な論理で彼らに寄り添わなければならない。
汎用的なマインドセットやフレームワーク
まず、HRTの原則(謙虚/尊敬/信頼の原則)の重要性は強く認識づけしておきたい。この原則についての解説、また僕がHRTに基づいた接し方を心掛けることによって知識/経験の両面からアプローチをかけ短期間でもその重要さ、あるいはHRTが染みついている人間との仕事のしやすさを理解体感してもらいたい。
また、それでも生まれくる過信や、感情/思考/事実がごちゃ混ぜになった愚痴などに対する建設的な解決方法も提案しておきたい。できること、できないことを明確にすることによる不安と期待のコントロール方法と名付け、私自身の経験に基づく事例からその失敗例、成功例を語ることとする。
最後に、悩むことと考えることの違いについても話したい。これは僕が高校生くらいの時からずっと言い続けている言葉なのだが、
悩むとは問題の輪郭をぼやけさせ、答えを遠ざける行為である。 考えるとは問題の輪郭を明確にし、答えに近づく行為である。
ここまでスライドや資料を作った上で、ある本を先日から読み始めた。

エンジニアリング組織論への招待 ?不確実性に向き合う思考と組織のリファクタリング
- 作者: 広木大地
- 出版社/メーカー: 技術評論社
- 発売日: 2018/02/22
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログを見る
昔一度読んだりしたのかというほどに、上記論理に酷似した経験的教えが載っていた。有効かつ広範にわたる様々な手法やマインドセットを盛り込んでおり、端的に言って名著である。もはやこの本を読ませればいいのではないかという気さえしてきた。しかし本では補えない部分、つまり僕の経験を交え真摯にこれらのことを伝えることで少しでも僕の熱量、心からのメッセージを彼らに残せるようにする努力は怠るわけにはいかない。
メリハリをつける
僕が最初に入った会社では、ウォーキング研修という前時代的悪意のある新卒研修があった。スタート地点からゴールまで、おおよそ40kmの行程をルート選定から秒単位のスケジュール立てなどを行い実際計画通り歩くという研修だ。ルート、速度、スケジュールを根拠と仮説の形式で先輩社員に提出し、先輩社員は儀式的にその不完全性を詰問する。これが二週間以上毎日毎日繰り返されてようやく当日歩くわけであるが、さらにそこに役員や中堅社員も同行することで更なるプレッシャーが掛けられる。
僕はこの研修について、非常に批判的であった。研修後はこのような圧をかけられることはなかったし、さらに言えば詰問してきた先輩たち自身もこの研修で学んだことを習慣化している様子はなかった。
しかし、僕は一つだけこの研修について評価しているところがある。それは「怒られる」ということを体験させている点である。それがあまりに理不尽で執拗であった故に僕は当時から人事や先輩社員を批判していた(そう考えれば先輩も完璧ではないという副次的な学びもあった)が、ある程度の緊張感を持たせることは非常に有効であると思う。
よって、研修の一部分、要件定義の部分では彼らにグループワークをさせて、あくまで論理的に過不足を指摘し過信をたしなめるイベントを組み込む。過度の圧迫にはならないように、しかし学生生活の中で育まれた馴れ合いの文化が通用しないことに気付かせる程度には刺激を与えたい。
さいごに
数々の困難が彼らに待ち受けているであろうこと、その辛さを隠さないで欲しいこと、休むことは罪ではないこと、あなたは完璧ではないし、また我々も完璧超人ではないこと、競争相手ではなく、同じ方向を見ているだけの個人であることをしっかりと彼らに伝えたい。
ALLY認定講座(セクシャルマイノリティ研修)を受けた僕が思うこと
アライとは
「アライ」とは、英語で「同盟、支援」を意味するallyが語源で、LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー)の当事者ではない人が、LGBTに代表される性的マイノリティを理解し支援するという考え方、あるいはそうした立場を明確にしている人々を指す言葉
(引用元:https://jinjibu.jp/smp/keyword/index.php?act=detl&id=738)
社内でセクシャルマイノリティに関する任意参加の研修があるとのことで、参加してきた。身近にセクシャルマイノリティの方が多く、大学でも専攻と言うほどではないがジェンダー論をそれなりに学んできたことから、何か自分にとって刺激になるのではないかとの思いで参加を決めた。
これは本当に偶然なのだが、前回のエントリも性差別(にまつわる僕の無自覚の罪)について書いており、性というものは最近何かと僕の中でホットな話題になっている。そういえば以前にも男性学についてちょっと書いた。
三浦しをんさんが女性だと知って僕はショックを受けた - ここはクソみたいなインターネッツですね
アライ、というものは"ストレートアライ"とも言うそうで、主として自身はLGBT(orセクシャルマイノリティ)ではないという前提のもとで名乗る存在らしい。まずこのアライという存在、概念を知れたのは大きな収穫だった。受講した研修によればアライという存在はあくまで排他的マジョリティとマイノリティの間に立つ存在、つまりはマイノリティの理解者であり、排他的思想を批判したり啓蒙活動によってマイノリティへの理解を世界に強いるような存在ではないという。排他的思想自体も一つの多様性として受容し、あらゆる多様性を認め理解を示す。この一見不明瞭というかフワッとした印象を与える立場および目的こそがアライという概念の核であると僕は理解した。
LGBTという言葉に関して思うこと
大学で多少のジェンダー論を学び、社会人になってこのような研修を受けて尚、やはり僕はどこかこの性という領域の話に引っかかりを感じている。
まず初めに、僕の立場を表明しておく。僕はセクシャルマイノリティという表現は適切でないと考えている。この表現は当事者に対しある種のラベリング的なニュアンスを含んでしまうし、マジョリティ対マイノリティという構造、及びその認知を助長し得る。構築主義者の立場をとるつもりも構造主義(ポスト構造主義含む)的視点からものを述べるつもりもないが、世間が真の意味で多様性を認めることを正義だとするならば、そもそもこの領域に特別な表現や呼称の存在を許容してはならないはずである。誰がどんな立場でどのように性を受け止め考え行動しようが全て「普通」とするのが自然なのではないかと思う。今回の記事では便宜上セクシャルマイノリティという表現を多用するが、しかし本当のところはその言葉さえ失われるべき表現であると考えていると表明したい。
世間ではLGBTという言葉やレインボーの印(🏳️🌈)がセクシャルマイノリティのアイコンとして広く認知されていることに異論はないであろう。しかし、LGBTという言葉は決して全てのセクシャルマイノリティを包括しているわけではないということも注釈しておかなければならない。
そしてそもそもLGB(レズビアン・ゲイ・バイセクシャル)は性的指向の話であり、T(トランスジェンダー)は生物学的性と性自認の不一致の話であるからして、これらが一緒くたにされているのは妙な話である。また、トランスジェンダーの話をするにあたっては性同一性障害(GID)という障害との違いを明確にしなければならない。それを明確にするためには更に"障害"という概念についての説明が必要になる。かなりややこしい話になるが、一つずつ考えていきたい。
本領域における「障害」の様々な定義
障害という言葉についての辞書引きは省略するとして、障がい者についての日本における法律上の定義を障害者基本法の第2条(定義)に当たることとする。
障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
重要なのは「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態」と定義されている点。次に、病名としての性同一性障害の公的な定義に当たりたい。
性別といえば、男性か女性の2種類に分かれると多くの人たちは単純に考えます。しかし、性別には生物学的な性別(sex)と、自分の性別をどのように意識するのかという2つの側面があります。性別の自己意識あるいは自己認知をジェンダー・アイデンティティ(gender identity)といいます。多くの場合は生物学的性別と自らの性別に対する認知であるジェンダー・アイデンティティは一致しているため、性別にこのような2つの側面があることには気づきません。しかし、一部の人ではこの両者が一致しない場合があるのです。そのような場合を「性同一性障害」といいます。つまり、性同一性障害とは、「生物学的性別(sex)と性別に対する自己意識あるいは自己認知(gender identity)が一致しない状態である」と、定義することができます。
(引用元:厚生労働省 みんなのメンタルヘルス - 性同一性障害)
この定義が厚生労働省の見解なのか日本精神神経学会の助言を受けての見解なのかはわからないが、この定義は大きな誤りを含んでいる。もしこの定義を是とするならば、全てのトランスジェンダーを「障害」として位置付けてしまうことになる。障害者基本法における「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態」という要件がすっぽり抜け、あまりに杜撰に「性同一性障害」を定義している。
実際に厚生労働省がこういった定義をしたのかあるいは委託先相談先の人間がそうしたのかは先述した通りわからない。しかし、省庁のページにこのような飛躍した正確でない定義を載せるのはいただけない。
実は障害者基本法とは別に性同一性障がい者に関する法令は存在しており、そちらでは性同一性障害を以下のように定義している。
第二条 この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。(性別の取扱いの変更の審判)
(引用元:性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律)
僕としてはこちらの定義の方がより正確なものであると感じる。「自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者」という本人の意思を加味している点が先述の厚生労働省による定義との大きな違いである。即ち、トランスジェンダーであることと性同一性障害であることは必ずしも同一ではない、ということが読み取れるのだ。僕は正にそこに引っかかっている。トランスジェンダーは性(及び性自認)の多様性であり、それを認めようという話をしているのだから、病名としての性同一性障害と同一視することは何かひどくおかしな事のように感じられる。
決してトランスジェンダーの方を擁護して性同一性障害の方を誹謗しようというねらいや、またその逆もない。僕は概念的に別のものであるべき二つのものを同一として捉えていることについて、単純に引っかかりを感じているのである。
さらに言えば、性同一性障害を「障害」と呼ぶことにも違和感を覚えている。先に挙げた性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律や他の法律において、性別適合手術を行うために必要な医学的(病理学的)診断名として性同一性障害という名前を使っていることは理解できる。また、社会福祉の観点において障がいというくくりを与えることの利益も多少なれ想像できる。他の精神障がい、知的障がい、身体障がいと同様の扱い(あるいは内包)をすることでそれらに対する福祉と同様の福祉が提供できるという、福祉の拡張性を重視した論理からこのような状況になっているのだろう。
性同一性障害に関して思うところはたくさんあり、この場では語りつくせない。よってここではブルーボーイ事件を紹介し当領域における日本の司法の致命的な失敗、その後にわたる法整備の遅れの文脈を指摘するにとどめる。
加えて、アメリカ精神医学会による診断分類(DSM)ではDSM-5において「性同一性障害」という表現を「性別違和」という表現に修正したことにも触れておきたい。先述したように、現代日本の法律や医療制度において障害か障害でないかという区別が必要であるという文脈には一定の理解ができるし、障害という言葉用いている法令や日本精神神経学会(だけなのかは分からないが)を責めようというわけではない。しかしやはり(アメリカを世界の基準とすることの是非は置いておいて)世界的、時代的な潮流と鑑みるに障害という表現は改善の余地があるように感じられる。これは他の障がいにおいても同様である。
そもそも「マイノリティ」というのは本当なのか?
LGBTという言葉が全てのセクシャルマイノリティを表現出来ているわけではないということは先述した。では他にどの様なものがあるか例に挙げると、アセクシャル、ノンセクシャル、パンセクシャルなどがある。性自認や性的指向はデジタルな区分でなくグラデーションのように多様であるから、全てのマイノリティに名前をつけることは非常に難しい。そして名前をつける行為自体について、僕は文頭で表明したように反対の立場をとる。しかし今回は論理展開の都合上パンセクシャルに注目してもらいたい。
パンセクシャルは全性愛と訳されることもあるが、ここでは当事者であると自認されている方が「しっくりきた」と仰っている定義を挙げる。
引用元:パンセクシャルとバイセクシャルの違いをパンセクシャル当事者が語ってみた|LGBTメディア|Rainbow Life
しばしばB、バイセクシャルと混同されるパンセクシャルだが、「そもそも性別を気にしない」という点がバイセクシャルとの違いだと言える。
上記記事にも同様の事が書いてあり非常に共感を覚えたのだが、僕はこの定義を初めて見た時、今のパートナーが性適合手術を受けたいと言った時のことを想像した。パートナーの性的指向は引き続き僕の性に合致するとして、僕は性を訂正したパートナーとどう付き合っていくのだろうか。そのことを原因に離れるのかどうか。この問いはあまりに本質的であり、僕が「マイノリティ」という言葉に疑いを持つようになった理由である。
人によって違いはあるが、ホルモン注射による性適合(身体的な性の特徴を得る)過程には3〜4年の歳月がかかると当事者の方がおっしゃっていた。即効性のあるものではなく、徐々に移り変わっていくのだという。これが正しいとすると、もしパートナーが性適合をするとしても、直ちにその変化か目に見える形で現るわけではないということになる。
ならば、その時点ですぐさま問題となるのは将来の話のみである。当然のことながら、理想とする将来像、譲れないパートナー選びの基準やそれ自体の有無は人によって違う。この時生まれる判断軸を想像するに、大きくは六つ程の問いが生まれるだろう。
第一に、子供を残せるか残せないか。
第二に、同性の特徴(性質)を持つ人と生きていくことに自身の中で抵抗があるかないか。
第三に、社会的性別役割や性における封建的規範をパートナーに期待するかしないか。
第四に、世間における見え方を受容できるかできないか。
第五に、性が訂正されても同一の人間であると思えるか思えないか。
第六に、全てを差し置いて共に生きたいと思うか思わないか。根源的かつロマンティックな問いである。上記五つの問いは全て、結局のところこの問いに回帰する。
言うまでもなくこの段階で別々の道を歩むことを選択する人は当然いるだろう。そういった人を責めも擁護もするつもりはない。しかし、それが多数派であると断ずることについてはあまりに早計で、無根拠であると僕は考える。
加えて、パートナーの身体的性が訂正されていく過程を想像する。日々変化(修正でも訂正でも適合でもよい)していくパートナーを見て、僕は何を思うだろう。例えば体重の増減で考えてみよう。パートナーが少しずつ体重を増していったとして、その変化に強烈な違和感を覚えることは果たしてあるだろうか。僕の経験的範疇において、そんなことはないと断じよう。それと同様に、パートナーの身体的精神的性質が他の性へと転換されていくことで起こる関係の変化は、あるとしても緩やかかつ些細なことのように思える。それは果たして年齢を重ね考え方や価値観が変化していくことと、どれほどの違いがあるのだろう。そして、パートナー自身が性適合していく自身を喜んでいる姿、言い換えれば、願いを叶え幸せを得ていくパートナーを否定的なまなざしで捉えることができる人間はどれほどいるのだろう。
先ほどの六つの問いに、一つ一つ僕なりの答えを出していくとしよう。
- 子供を残せるか残せないかは僕にとってパートナーの判断基準にはなり得ない。
- 同性の特徴を持つ人と生きていけるかどうかは、その状況にならなければわからない。
- 社会的性別役割やその規範などそもそも僕の中には存在しない。
- 世間というものに恭順して生きたことはない。
- 性が訂正されても同一人物は同一人物である。向精神薬や抗不安薬によって気分を調整したとしても、僕は僕であると自認できることからそう言い切れる。
- そもそも上記五つの問いは僕にとって問題たり得ない。そして、全てを差し置いてでも共に生きたい。少なくとも今は現在のパートナーについてそう考えている。
また、僕はパートナーの喜びを共に喜べるような人間でありたいと願う。
よって、僕は自身についてパンセクシャルになり得ると結論した。この投稿をするにあたって、念のためパートナーに確認した。彼女は現在身体的性も性自認も女性であり、性的指向は男性であるそうだ。僕はそのことに少しの安堵感も覚えなかったことから、上記結論及びその論理強度に感情的強度を付与したことを記しておく。
では、僕のような人間が特殊なケースなのかどうか。統計的に証明しようとしても、この件に関しては慎重な自問自答と具体的な想像を経た人からデータを取らなければ意味がなく、困難である。その上、もし僕を特殊だとする立場の人がいたとして、その方がそう思えるパートナーを獲得していないからそう考えた可能性もある。未だ残る社会通念上の誤解や印象により僕のような人間に忌避感を持つ人でも、社会が変わればその忌避感が失われる可能性は大いにある。また、動物的本能が種を残そうとするのだから同性愛や子孫を残せない性的指向はやはり不自然だという論もあるだろう。僕の不勉強故に生物学やその類の学問のことはわからない。もしかすると生物学的にはそうなのかもしれない。しかし高次脳がこれほど発達した人類が生み出した社会および文化において、セクシャルマイノリティが多様性として受け入れられようとしている今、そのような本能がどれほど人間に対し威力を持っているのか僕は疑問に思う。
結論
つまり、誰もがセクシャルマイノリティになり得る可能性を持っており、であるならばセクシャルマイノリティはもはやマイノリティとは言えないのではないかというのが僕の主張である。
尚、本記事において様々な表現を用いましたが、特定の性、障がいをもつ方、また持たない個人を差別、攻撃する意図は全く御座いません。
三浦しをんさんが女性だと知って僕はショックを受けた

- 作者:しをん, 三浦
- 発売日: 2011/02/26
- メディア: 文庫
何がショックだったかって、僕が三浦しをんさんを男性だと思ってしまっていたこと、つまりは未だ無意識の内に性差別的観点を蔓延らせていること、そしてそれを少しも自覚していなかった自らの愚かさだ。
彼女の本は「きみはポラリス」、「舟を編む」、「私が語り始めた彼は」などからはじまりそれなりに読んでいたつもりだった。凄まじい程に巧妙で的確、そして美しい文章を書く人だなあとずっと思っていた。二、三頁に一文は必ず「言葉でこんなことを描ける人間がいるのか」という驚きと確かな敗北感を覚える文章がある。それくらい三浦しをんさんは素晴らしい作家だ。
恐らく、その敗北感が僕を錯覚させたのだと思う。こんなに凄い文章を書く人はどんな人だろう、内に秘めた暗さをこんなにも明らかに隠せる人はどんな人なのだろう。そして、「しをん」という筆名を選んだ人はどんな人なのだろうか。僕の想像は、気が付けば一人の若い天才的なセンスを持つ男性を作り上げていた。これまでの人生から、友人から家族から、大学から社会から、僕は性に対する偏見の理不尽さ、罪深さをたくさん学んできたはずなのに、なんとなくのイメージで三浦しをんさんは男性だと思ってしまっていた。
もしこの誤解が彼女の文章に対する敗北感に由来するものだとすれば、口では男女に優劣など一切ないと言い、頭と心もそれに同意していたつもりでも、それは表面上のポーズに過ぎなかったのかもしれない。つまり、僕は心や頭の奥底で女性蔑視、性差別をしてしまっていたのではないか。そうは思いたくないが、そうだとしたら僕は僕が軽蔑する人間達と同じになってしまう。
僕が最初に『秘密の花園』を手にしていればこの勘違いは起こらなかったかもしれない。秘密の花園は非常に女性らしい繊細なお話だ。女子校に通う少女をこれほどの浮遊感と開放感に満ちた文章で包みこむ作品は男性には作れないのではないかと気付けたかもしれない。
しかしこれまで読んできた彼女の作品は、僕を完璧に騙した。彼女の本を読めば読むほど、この本の著者は僕のいる世界とは隔絶された次元からこの世界を覗いているのではないかと思わせられる。精密で大胆な描写、その確かな実力を敢えて見せつけるでもなく淡々と想像を絶する着眼点で人の想いを世界の動きを表現する胆力。どれを取ってもこの人は天才だ。
そして何より、彼女は人の感情を論理的に描写できる数少ない作家だ。多くの作家は登場人物の激しい感情を描写する際に少し突拍子にも思える表現やセリフを言わせる。それは敢えて動的なリズムを文章に取り入れるという目的のものもあれば、作者の力量不足で止むを得ずそうなってしまっていることもある。
しかし、彼女の感情描写は驚く程滑らかに行われる。人の感情の揺蕩いの殆どは、突飛に見えどもそれなりの論理に基づいた波形の道程に過ぎない。桜が初春に蕾を蓄えやがて春には満開に、そして残花に侘しさを託して散りゆくが如く、人の感情の開花とはその足踏みから残心まで、前兆と余韻を持つものなのだ。感情、情景の機微をこれ程までになめらかに、鮮やかに、そして論理的に描ける作家はそうはいない。
その論理性にこそ騙された。彼女の描く論理の繊細さはややもすれば神経質にも思える類のものだ。神経質といえば男性、という僕の中に蔓延る一種の性差別が彼女に対する決めつけを起こした。性差別、ジェンダー差別、人種差別などクソ喰らえと公言している僕ですら、区別としての男女比較の範疇を超えた誤認をしていたというわけだ。
僕はショックだ。論理的で美しく整然とした文章を書く女性がいて何がおかしいというのだ。クソ食らうべきなのは僕の方だ。ちくしょう、差別的思想なんて捨て去ったと思ったのに社会は僕の無意識の部分にまで差別を植え付けている。跳ね除けてきた自信はあったのに、まったく敗北した。いつかこんな社会壊してやる
悪気はなくとも、言葉は人を傷つける。
コミュニケーションというものは難しい。適切な言葉を選んで発することも難しい上に、相手の話を聴きしっかりと理解することもまた更に難しい。
男性の友人と飲んでいたとき、会計を済ませた僕らを可愛らしい店員さんがエレベーターまで送ってくれたことがあった。
「お仕事お疲れ様です。明日からも頑張って下さい、またお待ちしております。」
柔らかな笑顔で気持ちよく僕らを送り出してくれた店員さんに対し、友人はこんな言葉をかけた。
お姉さん、もう少しお仕事頑張って下さい。
店員さんはその言葉を聞いてキョトンとしていた。友人も店員さんの反応が予想外であったのか、一緒になってキョトンとしていた。ほんの少しの時間が過ぎて、可愛らしい店員さんの笑顔が引き攣り始めたその時、僕はこのコミュニケーション齟齬の全てを理解した。
僕の友人は、店員さんに対して「お前は仕事が出来ていないからもっと頑張れ」と叱責したのではなく、「閉店まであと少しの時間ありますが、お姉さんもそれまで頑張って下さい」とエールを送りたかったのだ。
しかし店員さんはそれを叱責だと受け取り、さっきまで上機嫌そうにしていた客が急にマサカリを投げつけてきたことに困惑する。友人は友人で丁寧に相手を労ったはずなのに、微妙な間を作り出してしまったり笑顔を引き攣らせた理由が分からず困惑する。
僕は慌ててディスコミュニケーションの構造を二人に説明した。店員さんは「なるほど!怒られたのかと思いました。」と笑顔を取り戻し、友人は「ありがとう、危うくサイコパスかなにかに見られるところだった」と胸を撫で下ろしたようだった。
昨今ではメールやチャット等、文面でのコミュニケーションをとることは誰もがやっていることであると思う。リモートで働く人も増えているし、そもそも対面でコミュニケーションを取ることをコストとして捉える風潮もある。しかし、情報量の多い対面のコミュニケーションでさえ先述した友人と店員さんのようなディスコミュニケーションは生まれてしまうのだから、文面ではもっと頻繁に、より悲惨なことが起きていると推察するのは自然なことだろう。なればこそ、我々は特に文面上のコミュニケーションを行う場合は普段より互いを気遣うべきだ。
言葉の重み
僕は基本的に大切な友人や恋人とはあまりラインやメールでのやり取りは行わないようにしている。表情の作り方、声のトーン、話すスピード、イントネーション、善意/悪意の有無、感情の強さ。これらの情報が付与されないコミュニケーションを苦手に思っている。恐れていると言ってもいい。
僕の言葉は率直すぎるというか、短慮になってしまうことが多いようで、気付かぬ内に人を傷つけてしまうことが今まで度々あった。基本的に人に嫌われたくない人間であるはずなのに、人を傷つけてしまっていて、それに気づくことさえ出来ていなかった。僕の言葉で傷ついた人がいるという事実を人伝に聞いた時なんかは結構ショックを受けた。それはもう、少なくとも二、三日引きずって落ち込むくらいに。
そういった経験から、僕は状況に合わせて慎重に言葉と態度を伝えることを心がけるようになった。当然今それが完璧に出来ている訳ではないし、考えるのが面倒になって短慮な言葉を発してしまうことも多々あるが、なるべく不本意な状況を作らないよう気をつけている。
それでも、やっぱりコミュニケーションは難しいと感じる。例え僕が本当に慎重に言葉を選んで大切なことを伝えようとしたとしても、相手がそれをどう取るかは結局のところわからない。僕なりに心を込めたメッセージを発したとしても、その重みや思いが相手にうまく伝わらないことはある。それは相手と自分の関係性の影響もあるし、自分の普段の立ち居振る舞いがそうさせているのかもしれない。
同じ言葉でも、誰にそれを言われるかで受け取り方や感じる重みは違う。僕の言葉や考え、アドバイスなんかを「そうだよね」と納得してくれたとしても、それが表面上の納得に過ぎず、「こうしたらいいかもしれないよ」と伝えたことが実行されないなんてよくあることだ。
よくあることなんだけれども、そういう時、僕は悔しさというか、不甲斐なさのようなものを強く感じる。うまく伝えることが出来なかった、僕では役に立てなかった、そんな思いが心の奥底にポツンと種のように残り、いつかパキパキと音を立てて発芽してしまうのではないかというぼんやりとした不安を覚える。でも、それってしょうがないことなんだと思う。
逆に、僕がそれほど重みを持たせずに発した言葉が相手には重く伝わってしまうこともある。それがひどく相手を傷つけることも。僕の軽い言葉で誰かが傷つくということは、つまりその誰かは僕の言葉を真摯に聴いてくれようとしていたということだ。そんなに僕を大切に思ってくれている人を傷つけてしまうなんて、本当に怖いことだ。傷つけるつもりはなくとも、言葉は時に相当な威力を持ってしまう。その刃は相手にも自分にも向けられる。
元気のない時期、単刀直入に言えば鬱病を患っていた時期に、僕はたくさんの人からアドバイスや心配の言葉をもらった。多くの人が、おそらく僕のためを思って本心から心配してアドバイスをくれていた。けれども、僕がその重さをしっかりと理解できていたかと言われると、わからない。もしかすると、僕に優しくしてくれた人々も、僕が感じるような悔しさを感じてしまっていたのかもしれない。僕が、そう感じさせてしまったのかもしれない。それを申し訳なく思う一方で、僕は僕が慎重に選んだ言葉の重みを理解して欲しいと願ってしまうエゴも捨てきれない。
そんなのは結局お互い様だ、と簡単に言ってしまうことはしたくない。簡単な話ではない気がする。物質世界において、言葉に重さなんてものはないのだけれど、でも、言葉の重みというものは確かに存在する。この話を難しくしているのは、それを計る尺度が人それぞれ違って、またその尺度自体も状況や相手、感情や思考によって大きく変化をすることだ。だからこそ、言葉の重さがもたらす問題と折り合いをつけるのはとても難しい。自身を省みて、相手にエゴを押し付けないようにしなければならない。そんなことが出来る清い人はなかなかいない。
そんな人はなかなかいない。そんなことはなかなかできない。けれども、僕ら人間はコミュニケーションを取らずにはいられない。面倒で、難しいことで、厄介なことで、大変なことなんだけれども、やっていかなければならないことなんだ。それがとても、僕には難しいよ。