男性学について
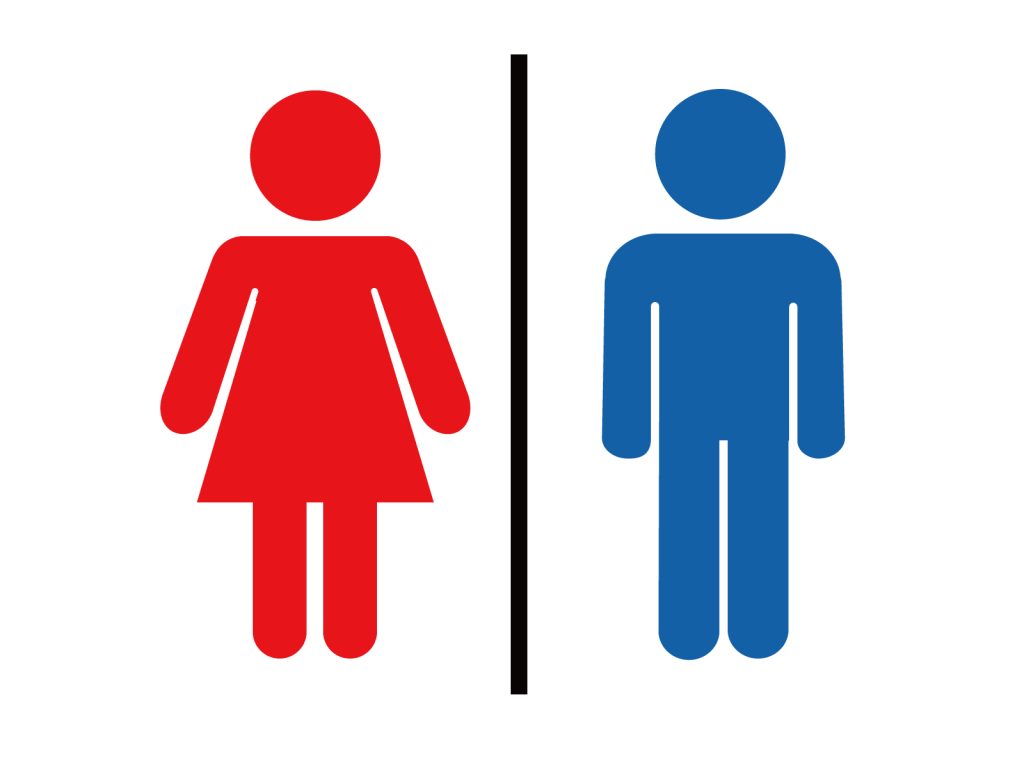
男性学とは何か
男性学とは、文字通り男性についての学問である。
ジェンダー領域において、女性についての議論は常に意識され、十分とは言えずともそれなりに発展してきた。それは男尊女卑の歴史への反発からとも、文化水準の高まりが人々に知性をもたらしたからとも言える。
しかしその一方で、男性に焦点を当てたジェンダー論は長い間見過ごされてきた。 女性には女性の生きづらさが、男性には男性の生きづらさがある。
ならば女性のことだけではなく、今一度男性の生きづらさ、男性らしさとは何なのか見つめ直そう。 そうした動きから、男性学が生まれた。 歴史上培われた「男性らしさ」という偶像は、今や男性を苦しめる枷となっている場合がある。「自分らしさ」を追求することが美徳となりつつある現代において、僕たちは「らしさ」の呪縛から逃れられない。「男性らしさ」というものは、あまりにはやすぎる時代の変化に追い付けない。男性学は、そのギャップに深く切り込む。
恋愛の男性学
女性は守られるもの、男性は守るもの。
女性の自立を促進させようとする社会の動きがある一方で、こういった思想は未だ色濃く残っている。
それは人々の中だけではなく、社会システムとしての「常識」にまで存在している。女性が男性の戸籍に入籍する、という通例は正にそれを示している。この思想の由来が男性にあるか女性にあるかという問題は難しい。鶏が先か卵が先か、という水掛け論にしかならない。男性が示威のために女性を「所有」しようとしたのか、女性が保身のために「所有」されることを望んだのか。歴史を鑑みても、その答えはきっと見つかりはしない。
2000年代中ごろ、「草食系男子」という言葉が流行した。初めて命名された時期については諸説あるが、2006年の深澤真紀による日経ビジネスオンラインにおける記事が初めて使われたという説が主流である。深澤によると、その定義は
恋愛やセックスに「縁がない」わけではないのに「積極的」ではない、「肉」欲に淡々とした「草食男子」です。
(日経ビジネスオンライン U35 男子マーケティング図鑑 第5回 草食男子http://business.nikkeibp.co.jp/article/skillup/20061005/1... より抜粋)
とされている。また、1994年にギルマーティンが提唱した「シャイマン・シンドローム」という概念がある。こちらは端的に言えば「恥ずかしがり屋」な男性のことを示している。
草食系男子とシャイマン、これらはそもそも男性が積極的に女性に関わろうとする、という暗黙の前提から生まれた言葉である。 真の意味での男女平等が叫ばれている現代社会にも、いかに色濃く男性主導文化の名残が存在しているかがこのことからも見える。そして、そこに「意識のギャップ」のようなものが生まれつつあるからこそ、草食、シャイマンのような概念が流行しているのではないか。 また、インターネットの台頭、更に言えばe-mailの普及がそのギャップ認識を加速度的に人々に広める装置となったとも考えられる。e-mailは私たちに、敷居の低いコミュニケーションをもたらした。結果として恋愛までの道のりは簡略化され、恋愛自体が「常識」として人々に浸透していった。
現代の若者の間では、恋愛は半ば義務化しているといっていい。その証明として、アミューズメント産業や食品産業がクリスマスやバレンタインを「市場」として捉えていることは今更言うまでもない。 パートナーが居る、ということがある種のステータスとなり、反対にパートナーがいない人間はどこか欠陥しているという認識を持たれる。その現状を、当然のものとして人々が受け入れていることは言わば不気味なことだ。
男性学の課題は、問題を問題として認識することが第一の関門であると僕は思う。
そもそも「らしさ」というものについて男女間で認識を共有できていないという指摘もある。
女性は痩せ形のモデルに憧れることに対し、男性はふくよかな女性を好む。逆にボディビルダーに女性は強く反発するのに対し、男性はそれほど反発しない。
これは『女性学・男性学 ジェンダー論入門』(伊藤公雄 樹村みのり 國信潤子共著 有斐閣 2002年)の一部要約である。
これが正しいとするならば、男女共に異性の視線よりも同性の価値観を重要視しているとも考えられる。男の話をする女は、大抵女に対してその話をしているのである。
異性との交際がステータスであり、価値観を同性寄りに設定するのであれば、それは同性に対する自己演出の一環、言わばパフォーマンスとしての恋愛である。異性との恋愛は、同性という観客に向けて繰り広げられるものなのだ。
現代の若者達は主に同性という社会からの承認を求めており、その手段として恋愛をとっている。そして、それを相互に確認し合うことでアイデンティティを獲得していくというプロセスを持っているのではないか。大きい話をするわけではないが、晩婚化や少子化の要因の一部として、あるいはこの意識の変化が影響しているのかもしれない。
まとめ
以上の全てを文脈として捉えると、男女の「生きづらさ」はむしろ同性同士の間に生まれているものであるように思える。互いに悪循環を構成し、真の意味で「自分らしさ」を求めようとする時代の流れにうまく対応できていない。僕らの根底に存在している男女不平等感がさらなる不平等を生み、ステータスやアクセサリーとしての恋愛を互いに求めていることになる。
当然、「自分らしさ」というものを求めることについての是非はそれぞれの意見があっていい。しかしそれを望む人々にとってこの問題は大きな壁として立ちはだかることは確かだ。
グローバル化が進み、文化の進化はさらに加速していく。その中でこの問題は取り残されてしまう。人々の認識を深めない限りは表立って何か事が起こることはない。解決すべきであるか、放置すべきであるか、安易な結論が出せる問題ではない。しかし、表面化しづらい問題こそが更なるうねりを生み出すのは世の常だ。「生きづらさ」に苦悩する僕ら自身が作り出す「生きづらさ」は、果たしてこれから僕らに何を齎すのであろうか。少なくとも僕は、この問題を認識する人々が少しでも増えることを望んでいる。
そしてなにより、なんかいい感じにかわいくて性格も良い女子高生が合法的にぼくの生きづらさを心身を持って解消してくれることを望む。
舌を舐める
やりたくもないことをしていると、自分自身とか自分の人生がどんどん摩耗していくばかりな気がしてしまう。
くだらない飲み会に使う時間も金も、全部人生を犠牲にしているって考えちゃうとなんだかね。 こんなことのために働いているのか、という命題からはこの先もずっと逃げられないのかもしれない。
じゃあ逆にさ、これをしている間は削られないっていうことはあるのかな。ふと今までを振り返って来て、これをしてよかったとか、これだけをしてたいとか。そんな風なことがあったろうか。
まあなんとなく楽しかったこと位は俺にもあるけれども、しかしそれが人生最高の瞬間と断言することは出来ないな。
その言い方をすれば、一方ではこの先の人生に希望を持っていると捉えることも出来る。けれども、これまで至上の瞬間を感じていないと捉える方が俺にとっては自然だ。
モテたくて始めたバンドのライブが成功したとき、まさに理想といえる女の子をみた時、友人とバカな話をしているとき。 全部素敵で嬉しい体験ではあったけれど、なかなかそれが最高だと言い切ることは難しいね。
時とともに精神は肉体は摩耗していくだなんて哲学的なことを言いたいわけではなくて、なんだかもっと「なんとなく自分っぽいもの」が削れていっている気がするんだよね。
例えば今まで、何かをしたいという気持ちと、何もしたくないという気持ちの総量を測っていたとしたら。何もしたくない、が90%以上を占めると思うんだよ。 よく、幸せと不幸は結局プラスマイナスゼロになるとか言うけれども、今のところそんなことないと思うね。今不幸だから、この先それが補完されるとバカみたいに信じる奴はいないよ。例えそう信じるしかない状況に陥った人がいたとして、なんならそれこそが人生最大の不幸だと俺は感じる。
自分が摩耗しない時間とか空間とか行為って、一体なんなんだろうね。空気に触れているだけで石が風化するというのなら、呼吸をしているだけで人も酸化するだろうよ。 ガリガリとエネルギーを削って、足りなければ身も心も差し出して。そうやってボロボロになった先に、きっと何もしなくていい空間、あるいはそれをくれる人が存在しているという希望に縋ってなんとかやってきた。 それがアルビノのように白くて細くて華奢で貧乳で俺のことを好きすぎてたまらない女の子であったり、そのこの胸のなかであったら尚いいと夢見てなんとかやってきた。
でも現実はさ。 たとえそれに近い女の子がいたとしても、男は守らなければいけないとか、俺にそんな魅力があるのかとかさ。そんなふうなノイズが鼓膜の中から鳴り続けているのさ。
やってらんないよね。なぜこんなにもたくさんのものとすれ違ってしまうんだろうか。
結婚報告とかプロポーズ報告とかをSNSで見たときに覚える感覚について。
プロポーズ報告を見るとウッと感じちゃうんだけどさ、 いやお前それ完全に妬みだろって言われたら何も言い返せない。 でも本当はそうじゃなくてもっと本質的に気持ち悪いモノを感じているのに、 何かコンプレックスが疼いてむしろ黙ることしかできなくなっちゃう。 で、なんなんだろうねあの感じは。 他人の幸福が嫌いだとか他人の不幸が好きだとか、 別にそんなに性格も頭も悪くないつもりなんだけれど。 それこそSNSだったりFacebookでもあるじゃない?プロポーズ報告とか。 なんかさ、どんな関係性の相手だとしてもその気持ち悪さは変わらないんだよね。 親友でも後輩でも先輩でも知人でも等しく気持ち悪い。 もちろんそれで人を嫌いになるとか、祝福しないとかそんなバカみたいなことはしないよ。 ただ本当に、気持ちがウッてなるんだよ。
2chとかでもあるじゃん、ほんわかエピソードみたいなの。 ああいうのも心底キモくてしょうがない。 その根底にはきっとさ、ああいう話がある程度世間を意識して対外的に作られた話だっていうのがあるんだと思うんだよね。 簡単に言うと、良い話としてその部分だけをまとめてるのがクソ気に入らない。 そんなアホみたいに綺麗で出来過ぎた話、信じらんねえよ。
お互い人生のパートナーとして共に成長していきたいとかさ、胡散臭いというかもうそれ本気で思ってるわけないじゃん。 そんな見栄えもよくて恥ずかしくない完璧な関係なんてさ、もうゆっくりと壊れていく未来しかないじゃん。 そんな物語なんてもう殺すしかないじゃん。 そうしないと話動かないじゃん。 そうしないと耐えられないじゃん。
だからさ「嘘ばっかり言ってんじゃねえよ」っていう気持ち悪さなんだよね多分。
人の汚い部分をみて安心する程頭が病んでるわけでもないけどさ、綺麗なモノに簡単に騙される程心が病んでるわけでもない。
その場で取り繕うことも祝福を強制させるなんてことも、どっちも本当に幸せな人間がすべきことじゃあないと思わない? 本人もやりたいわけじゃなくてやらされてるんだろうけどさ、文化だとしても意味わかんないよね。
お互いに気持ち悪いことだと知っていながら綺麗な関係を描くなんてさ、すげえ悪趣味な社会だよね。 悪魔じゃねえんだからそんなに人を騙すなよって思うわ。 地獄でもないんだからそんなに人を騙させるなよって話でもある。
で、その気持ち悪さにかなり近いものをもし自分が出してるとしたらさ、 「うるせえよ」っていうものなんだろうね。 皆が皆当たり前のようにやっている儀式とか儀礼とかをいちいち掘り下げてキモいとかいってるわけだしね。そりゃうるせえよ。
もちろんここに書いてるようなことはあんまり現実世界では話してないけどさ、世の中というか社会というか文化というか、そういうものってクソ気持ち悪いこと多くねえ? 最近本当気に入らないんだけど。だからってどうこう出来る問題じゃないのもまた気に入らない。 円滑さってそんなに快適か?自由って本当に自由か?みたいなそんな頭の悪そうな疑問ってなかなか答えが出てこない。
いつも何かにキレてるってほどでもないけど、いつも何かに批判的姿勢というか批判的疑問は持っていたい。
食傷気味の鰐とノスタルジア

世界の終わりなんて早々来るもんじゃあない。
ノストラダムスにマヤの予言、2000年問題なんかを経験した現代人には、そう気付いてしまっている人が余りに多い。
けれど一方で、本気で世界の終わりを願う人もまた余りに多くいる。
なんとも皮肉で可笑しいことだと思わないか。僕は本当にそう思うし、これから先もそうなんだと思うと何処か世界に安心する。
そういう話。
僕はオカルトが好きだ。とはいえ本気で幽霊だとかパワースポットを信じているわけじゃあない。現実的にそれらを意識するような経験も才能もないから、信じたくとも信じきれない。そう考えると本気でオカルトを信じている人は、特別な何かを持ち得た人なのかもしれない。
例えば一生をUFOに捧げて果てるだなんて、本当に才能だとしか言えないもんだろう。そんな大それたこと、僕に出来るわけがない。例えば他人の運命を占うだなんて、何も知らない僕がしていいことではない。
才能は適切な場所で生かされてこそ意味がある。これは僕が生きた短い時間で見出した唯一つの真理だといえる。 その点オカルトに熱中できる彼らは世間からいくら笑われようとずっと尊い場所にいる。夢物語のような不確かなものを信じているとして、それを内的に世界という単位にまで昇華させているのなら、もうそれは一つの現実と呼んでいい程の質量を持つだろう。
世界というのは迷惑なもんで、角度によって中々難しい表情を作る。僕と誰かがたった二人で存在している世界があるとして、結局のところ僕はそこに広がる無限の世界と対峙しなければならないことに変わりはない。人が二人以上いればそこにはどうしても社会というものが生まれてしまうから、僕はそんな状況でさえ、したいことだけをする人生などきっと送れない。
自分だけの世界、だなんていう言い回しがあるけれども、そんなものは存在しない。絶対に存在しない。UFOを追う彼も幽霊と踊る彼女も、彼らの中では何かしら対峙するモノが確実にあるはずだ。宗教家にとっての神が確実に存在するように、彼らにとっての相手はいつも彼らを見つめているものなんだろう。世間だったりお金だったり恋愛だったりを必死で追う当たり前の人々と、彼らは一体どう違うというのか。僕らと彼らでは、当たり前のモノが違うってだけの簡単な話なのかもしれない。
だとすれば、当たり前の僕は果たして何を追っているんだろうか。どんな才能があるんだろうか。その才能を持って、何と対峙し夢を見ているのだろうか。そんなことを胸に抱きながら今もなお、僕は自称女子高生を映す薄汚れたディスプレイを眺めている。
子供と大人の違い。

このテーマについて考えようとしたとき、真っ先に思いつくのは'夢'を見るかどうかだ。
「大人って、大きい子供なのよ。」
幼い頃、そう母に教えられたことがある。今思えば、なんとも的を射たことを言う。
その母は、五十いくらかの歳を重ねた今でも物語を愛し、理想や夢を語り子や孫に聞かせる。
彼女は随分と、子供らしい大人だ。
僕の記憶にある限りでは、自身のことを大人と称したことは一度もない。幼い僕の世界に対する疑問や好奇を、大人になれば分かると誤魔化したこともない。
子供の夢を聞き、一緒になって自らの過去の夢や今の理想を言葉に描く。
あまりに嬉しそうに夢を語る彼女を見て、ああ、大人になっても夢や理想というものは絶えないのか。と、無限の欲求というものの果てしなさを子供ながらに強く感じたことを覚えている。
そうして育てられた僕が確固たる夢を持ち得なかったのは必然と言え、彼女の教育の愛すべき過ちの一つと言える。
四半世紀以上生きた今、自分自身の事を、まだまだ子供だと思う。
しかし一方で、やはり社会は僕を子供扱いしてくれなくなり、今では被る責任も昔思い描いた大人のそれと変わらない重さを得た。
世間では、二十代や三十代はあっという間に過ぎていくなどと言われるけれど、僕は時の速度というものを意識したことがない。 僕にとって、それは常に一定で然るべきもののように思えて、今のところ速度はその意思に恭順してくれている。
一定の速さで時が流れるとすれば、ある瞬間から人が大人になるということはあり得ない。自立した瞬間からだとか、社会人になった瞬間からだとか、そんなことは本質から遥か遠くのまやかしを見る人間が言う言葉だろう。時の流れの中では、一切合切なにもかもが、グラデーションのように少しずつその色を変化させていくものであるし、そうあるべきだと僕は思うのだ。
ある時、友人がこう言った。
「子供の時はなんでも出来るって思っていたろ?けれども大人になっていくにつれて、人は少しずつ出来ないことを増やしてしまうんだ。自転車で青森まで行くことだって、子供の頃はきっと出来るって信じていた。でもいつの間にか、そんなことできるわけないって嘘を吐くようになってしまっていたんだ。本当は今だって、出来ないはずなどないのにね。」
大人とは難しい。
子供だって簡単じゃあない。
当然だ。大人なんて、少しずつ大きくなっていった、ただの子供なのだから。
できるはずのことを段々とできないことにしてしまう。
自分自身の限界を見定めるつもりが、いつの間にか限界を自分で決めてしまっている。
確かに年をとるということはそういうことなのかもしれない。
しかし悪いことばかりでもない。
この理論でいくと、何処にでもいるコンビニのレジのおばさんも、実は少しずつ大きくなった女子高生と呼べるわけだ。
意識次第で、僕の中及び君の中の女子高生は無限に増殖する。
女子高生しかいないなんて、世界がまた一つ魅力的に見えて来るだろう?
ぼくは世間一般でいう大人になってから、そんなことを考えて正気を保つようにしている。
社会の中で吹きすさぶ風や荒れ狂う波に揉まれながら、どこか遠くにいる女子高生のことをただ思いながらぼくは、生きているんだ。
教師は聖職者であるべきか生殖者であるべきか
教師たるもの、聖職者であれ。
教育を学ぶ者にとって、第一の壁はこの命題だ。本当に教師は聖職者でなければならないのか。教えによって人を導く者は、すなわち聖なるものであるべきなのか。
生徒はあらゆる経緯を経て、教師から「正しさ」を学ぶ。それが教師の正しさからくるものでも、誤りからくるものであったとしても、何かしらの正しさを自身の論理のもと学び取るのだ。生徒は教師から教えられるのではなく、自ら何かしらの正しさを学び取るために、注意深く教師を観察しているに過ぎない。
僕の経験から言えば、聖職者たりえた教師は居なかった。いつだって彼らは、彼らの教えと同様に不完全だった。高校生の頃、一年前まで教わっていた教師と駅で鉢合わせたことがある。稀にラーメンを奢ってくれることのあった彼が、どちらかといえば僕は好きだった。だからこそ懐かしさに胸を歓喜させ思わず声を掛けたのだが、しかし彼は僕のことを覚えてはいなかった。僕は教師と言えど人間である事をその時に知った。いや、思い出したと言った方がふさわしいか。
僕が教師から学んだ唯一つの確かなことは、「人間である以上、誤ることはある。」ということだ。誤りというものは生に密着したものであって、肉体、精神、態度、教え、思考、論理の全てに顕現し得る。
教師は、教室という閉鎖的な空間に絶対者として君臨する生き物だ。しかしそれが永続する訳ではない。ふとした瞬間に彼らの教室内での地位は地に落ち、教育の残酷さを身を以て知ることになり得る。彼らはその不安定な絶対性がもたらす自己矛盾の苦悩に常に晒される生き物でもあるのだ。真面目な教師であればある程、その特質は顕著といえる。
教師だって人間だ、という諦念を持ってしてその矛盾から目をそらすことも出来る。しかしそれは、多大な熱量を持って矛盾に立ち向かうことよりも、むしろずっと勇気のいる行為だと僕は思う。 僕が好きだった教育者は、ある時生徒の鋭い指摘にそうして視線を逸らした。その背徳は、少なくとも僕の眼には大変に尊い人間の自己防衛として映った。
客観的に見ればいくら教師だって人間なのは当然だ。堪え切れない欲望を持て余すことだってあるだろう。しかし、彼らにはいつも絶対者としての立場や責任が必要以上につきまとう。教師が痴漢をしようと一般的な会社員が暴漢になろうと、僕には別の事のようには感じられない。それが悪であり罪であるという話は別として、教師というものの社会的信用が失われるだとかそんな話に発展することが、不思議でしょうがないのだ。
教師たるもの、聖職者であれ。こんな言葉を言う人間は、人間に、あるいは人間が持つ聖なる部分に期待し過ぎなのだ。それは教師に対する教師らしさへの期待と同時に、生徒に対する生徒らしさへの期待も含んでいる。
教師から生徒へと話を移すと、生徒は、教師が痴漢を起こす前からずっと、彼らが決して聖職者たり得ないことなど気付いてしまっている。生徒は、教師が聖職者の仮面を必死に被ろうとしていることを、誰よりも知っているのだ。
教室というものは一つの儀式場だ。聖職者の仮面を被る教師に対し、その滑稽さを確かに知った上で生徒は生徒としての仮面を被る。教師と生徒の関係は、決して教育などというものではなく、仮面同士が擦れる静かな摩擦を味わう、ただ一つの儀式なのだ。
本当のところ、いい先生なんて居なかった。いい人間が、たまたま先生の仮面を被っていることなら何度か見たことがある。そんな程度の話だ。
教室などという儀礼の地獄に何時迄も居なければならないのだから、聡明な人にとっては教師は大変な職業だ。
生徒と教師だからといって、そこに愛が生まれただけで途端に騒がれる。人間と人間同士なんだ、何も問題などないじゃないか。やはり僕はそう思ってしまう。
物語は作者の手を離れるか

物語は、作者のみならず受け手にさえ創造的行為を求めている。そのような主張をしたのがロラン・バルトだ。
彼に影響された訳ではないが、私も物語は作者の手を離れるものであり、またそうあるべきものだと思っている。例えば100年以上もの間たくさんの人々に語られている童話に、著作権の議論や作者の議論を持ち出すことはナンセンスであると感じる。そういった議論が価値を持つのは、物語がどのような人々を経由してどのように進化を遂げたのか、という一点のみである。
童話に限らず、物語というものは少なからず独立性があるものだ。語り手によって、伝えようとする事柄も変化する。もちろんそれに伴い物語の筋も変化し、むしろ原型を留める必要性など欠片もないのだから、語られるたびに新しい物語が生まれているというべきだ。
漫画家の荒木飛呂彦が、最も古い職業は語り手なのではないかと言った。本当のところはわからない。娼婦が正解かもしれない。しかし彼のその言葉は夢のある言葉で、そして少しの現実味もある話であると思う。
物語というものは、作り手の想像を遥かに裏切る速さで伝染し進化する。いわばウイルスのようなものだ。語り手の数、あるいは受け手の数程それは膨れ上がり、いずれ自ら一人歩きを始める。 最低限の骨組みであったはずのそれも、いつからか必要以上の肉付きを抱き、最早骨組みの形状を無視した体型にまで進化する。
誰かが大事にしているプライドだとか、革命者のアナーキズムだとか、両親の優しさだとか。それらを全て内包する肉体は、誰が誰に宛てたものなのか、今ではもう誰にも分からない姿にまで成り果てている。 狡賢い高潔さと、理不尽な魅力。それだけをひたすらに表現する昔話・おとぎ話の類は、国境を越え、歴史を越え、人種を越えて語られる。そこには定義なんてものの居場所はなく、ちっぽけな規則など存在さえ許されない。 グローバリゼーションだとか、情報化だとか、そんな小手先の進化では汚せないほどの純粋さと、宗教だとか、努力だとか、愛情だとか、そんな小手先の退化では救えないほどの残酷さ。私はこれこそが物語の内臓であり、美しさとグロテスクさを感じさせる肝であると思う。 物語は人々の相互依存であり、鏡でもある。人々の創造力が作った一つの世界、というのはいささか夢想的すぎるか。しかしながら物語は人々の常識となり、宗教となり、文化となり、歴史となった。積み重なる歴史はいずれ世界を構築し、同時に観測者としての側面をも得始める。歴史に鑑みるという行為は、物語に鑑みるということである。物語が自動的に新たな物語を紡ぐようになったのならば、最早それは一つの世界であるといっていい。 物語の語り部として存在していたはずの誰も彼も、いつの間にか物語そのものに食い殺されていて、いつからかその内の一細胞として存在している。私は私の物語を語っているはずなのに、いつの間にか神の視点を持った「歴史」という世界の物語に取り込まれている。 こうした物語の多重性と神秘性こそ、物語が人を惹きつけて止まない重要な要素である。
姿を変え無限に進化する物語に、作者など必要ない。所有権を主張したいのであれば、物語を自らの中に閉じ込めておけばいい。しかしそれは物語を殺すことと同義である。
物語は生き物である。人という媒体に寄生させ、新たな栄養を取りこまなければ死んでしまう。作者に寄生し続ける物語があるとすれば、それは言語化されない単なる「妄想」でしかない。 似たような物語は各国にある。しかし物語というものの特質上、語り手や聞き手の違いが少しでもあるのであれば、全く同じ物語など一つも存在し得ない。そんなもの一つ一つに「作者」が現れて権利を主張するなど、最早喜劇の類いですらあると思う。 物語は作者など必要としていない。 ただ単に彼らは、媒体としての「語り手」を必要としているだけなのだ。