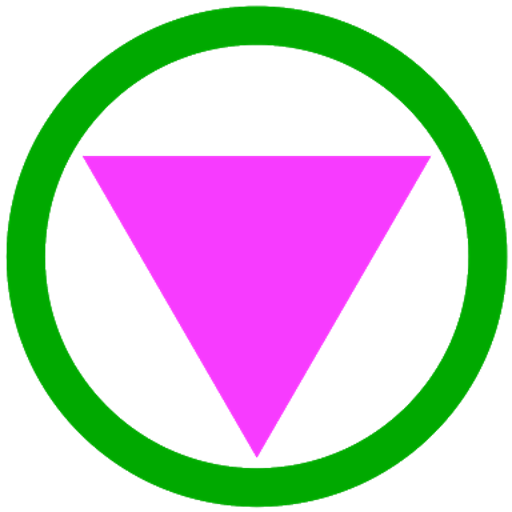新卒研修を行う上で僕が注意すること
入社半年なのに新卒研修を担当することになった
昨年12月よりエンジニアとして仕事をしている。入社から間もないにも関わらず、BTC(Business/Technology/Creative)人材育成研修のテクノロジー部分の担当として抜擢していただいた。これは僕がCODED@という学生向けプログラミング講師団体を立ち上げプログラミング講座を実施しているボランティア活動が評価されてのことだった。
プログラミング講座の方はCODED@のメンバーに了承を取り、普段実施している講座を流用することができるようになった。これはこのまま遂行できるとして、新入社員の方々とお話しできるせっかくの機会なので何か技術以外のことも伝えたい。
何を伝えるかの前に
何を伝えるか、という大きなテーマにいく前に、重要な点がある。コミュニケーションの第一歩は相手のことを知るということに始まる。つまり、一人一人の人生観、労働観、成長欲求、なりたい姿やその有無などを時間をかけてヒアリングをしなければならない。しかし今回は強い時間的制約が存在するため、そのような余裕がない。とはいえ、余裕がないからといって疎かにしていいものでもない。では翻って、僕が新卒だった時のことを思い出すことで少しでも彼らに近づいてみよう。
そもそも僕は新卒において、100%の確信を持って希望した会社に入ったという訳ではない。何をしたいのか、何ができるのか、何をすべきで何をしないべきなのか考えながら就職活動をしていたら、疲れてしまったのだ。なので真っ先に内定を出して下さったところに即決で入ることにした。もしかすると彼らもそうなのかもしれない。であるとすれば、次に僕が感じたのは「本当にここでよかったんだろうか」という漠然とした不安、「社会ってこんなものなのか」という今思えば傲慢ともいえる失望であった。空回りして自身の能力を過信してしまう時期など、多くの人が経験してきたよくある話なのだと思う。
全ての新卒が僕のように生意気であるとは限らない。しかし、彼らが漠然とした不安、言い換えるならば社会及び自身に対する期待のようなものを抱えており、それは非常な緊張と興奮による増幅に至っている可能性を頭に入れておかなければならない。一年目、というのは労働人生において大きな意味を持つとよく言われる。大筋には同意するが、僕の私見を加えるなら「一年目は思春期以来の多感な時期」であるからこそ意味を持つのではないだろうか。
人間は結論を出したがる生き物である。そして、この多感な時期には小さな出来事に大きな印象を抱きやすいきらいがある。つまり、彼らにとっての会社像、社会人像、さらに言えば大人像は研修担当によってある程度の指向づけが行われてしまいやすいのだ。このことを意識して、丁寧な論理で彼らに寄り添わなければならない。
汎用的なマインドセットやフレームワーク
まず、HRTの原則(謙虚/尊敬/信頼の原則)の重要性は強く認識づけしておきたい。この原則についての解説、また僕がHRTに基づいた接し方を心掛けることによって知識/経験の両面からアプローチをかけ短期間でもその重要さ、あるいはHRTが染みついている人間との仕事のしやすさを理解体感してもらいたい。
また、それでも生まれくる過信や、感情/思考/事実がごちゃ混ぜになった愚痴などに対する建設的な解決方法も提案しておきたい。できること、できないことを明確にすることによる不安と期待のコントロール方法と名付け、私自身の経験に基づく事例からその失敗例、成功例を語ることとする。
最後に、悩むことと考えることの違いについても話したい。これは僕が高校生くらいの時からずっと言い続けている言葉なのだが、
悩むとは問題の輪郭をぼやけさせ、答えを遠ざける行為である。 考えるとは問題の輪郭を明確にし、答えに近づく行為である。
ここまでスライドや資料を作った上で、ある本を先日から読み始めた。

エンジニアリング組織論への招待 ?不確実性に向き合う思考と組織のリファクタリング
- 作者: 広木大地
- 出版社/メーカー: 技術評論社
- 発売日: 2018/02/22
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログを見る
昔一度読んだりしたのかというほどに、上記論理に酷似した経験的教えが載っていた。有効かつ広範にわたる様々な手法やマインドセットを盛り込んでおり、端的に言って名著である。もはやこの本を読ませればいいのではないかという気さえしてきた。しかし本では補えない部分、つまり僕の経験を交え真摯にこれらのことを伝えることで少しでも僕の熱量、心からのメッセージを彼らに残せるようにする努力は怠るわけにはいかない。
メリハリをつける
僕が最初に入った会社では、ウォーキング研修という前時代的悪意のある新卒研修があった。スタート地点からゴールまで、おおよそ40kmの行程をルート選定から秒単位のスケジュール立てなどを行い実際計画通り歩くという研修だ。ルート、速度、スケジュールを根拠と仮説の形式で先輩社員に提出し、先輩社員は儀式的にその不完全性を詰問する。これが二週間以上毎日毎日繰り返されてようやく当日歩くわけであるが、さらにそこに役員や中堅社員も同行することで更なるプレッシャーが掛けられる。
僕はこの研修について、非常に批判的であった。研修後はこのような圧をかけられることはなかったし、さらに言えば詰問してきた先輩たち自身もこの研修で学んだことを習慣化している様子はなかった。
しかし、僕は一つだけこの研修について評価しているところがある。それは「怒られる」ということを体験させている点である。それがあまりに理不尽で執拗であった故に僕は当時から人事や先輩社員を批判していた(そう考えれば先輩も完璧ではないという副次的な学びもあった)が、ある程度の緊張感を持たせることは非常に有効であると思う。
よって、研修の一部分、要件定義の部分では彼らにグループワークをさせて、あくまで論理的に過不足を指摘し過信をたしなめるイベントを組み込む。過度の圧迫にはならないように、しかし学生生活の中で育まれた馴れ合いの文化が通用しないことに気付かせる程度には刺激を与えたい。
さいごに
数々の困難が彼らに待ち受けているであろうこと、その辛さを隠さないで欲しいこと、休むことは罪ではないこと、あなたは完璧ではないし、また我々も完璧超人ではないこと、競争相手ではなく、同じ方向を見ているだけの個人であることをしっかりと彼らに伝えたい。
ALLY認定講座(セクシャルマイノリティ研修)を受けた僕が思うこと
アライとは
「アライ」とは、英語で「同盟、支援」を意味するallyが語源で、LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー)の当事者ではない人が、LGBTに代表される性的マイノリティを理解し支援するという考え方、あるいはそうした立場を明確にしている人々を指す言葉
(引用元:https://jinjibu.jp/smp/keyword/index.php?act=detl&id=738)
社内でセクシャルマイノリティに関する任意参加の研修があるとのことで、参加してきた。身近にセクシャルマイノリティの方が多く、大学でも専攻と言うほどではないがジェンダー論をそれなりに学んできたことから、何か自分にとって刺激になるのではないかとの思いで参加を決めた。
これは本当に偶然なのだが、前回のエントリも性差別(にまつわる僕の無自覚の罪)について書いており、性というものは最近何かと僕の中でホットな話題になっている。そういえば以前にも男性学についてちょっと書いた。
三浦しをんさんが女性だと知って僕はショックを受けた - ここはクソみたいなインターネッツですね
アライ、というものは"ストレートアライ"とも言うそうで、主として自身はLGBT(orセクシャルマイノリティ)ではないという前提のもとで名乗る存在らしい。まずこのアライという存在、概念を知れたのは大きな収穫だった。受講した研修によればアライという存在はあくまで排他的マジョリティとマイノリティの間に立つ存在、つまりはマイノリティの理解者であり、排他的思想を批判したり啓蒙活動によってマイノリティへの理解を世界に強いるような存在ではないという。排他的思想自体も一つの多様性として受容し、あらゆる多様性を認め理解を示す。この一見不明瞭というかフワッとした印象を与える立場および目的こそがアライという概念の核であると僕は理解した。
LGBTという言葉に関して思うこと
大学で多少のジェンダー論を学び、社会人になってこのような研修を受けて尚、やはり僕はどこかこの性という領域の話に引っかかりを感じている。
まず初めに、僕の立場を表明しておく。僕はセクシャルマイノリティという表現は適切でないと考えている。この表現は当事者に対しある種のラベリング的なニュアンスを含んでしまうし、マジョリティ対マイノリティという構造、及びその認知を助長し得る。構築主義者の立場をとるつもりも構造主義(ポスト構造主義含む)的視点からものを述べるつもりもないが、世間が真の意味で多様性を認めることを正義だとするならば、そもそもこの領域に特別な表現や呼称の存在を許容してはならないはずである。誰がどんな立場でどのように性を受け止め考え行動しようが全て「普通」とするのが自然なのではないかと思う。今回の記事では便宜上セクシャルマイノリティという表現を多用するが、しかし本当のところはその言葉さえ失われるべき表現であると考えていると表明したい。
世間ではLGBTという言葉やレインボーの印(🏳️🌈)がセクシャルマイノリティのアイコンとして広く認知されていることに異論はないであろう。しかし、LGBTという言葉は決して全てのセクシャルマイノリティを包括しているわけではないということも注釈しておかなければならない。
そしてそもそもLGB(レズビアン・ゲイ・バイセクシャル)は性的指向の話であり、T(トランスジェンダー)は生物学的性と性自認の不一致の話であるからして、これらが一緒くたにされているのは妙な話である。また、トランスジェンダーの話をするにあたっては性同一性障害(GID)という障害との違いを明確にしなければならない。それを明確にするためには更に"障害"という概念についての説明が必要になる。かなりややこしい話になるが、一つずつ考えていきたい。
本領域における「障害」の様々な定義
障害という言葉についての辞書引きは省略するとして、障がい者についての日本における法律上の定義を障害者基本法の第2条(定義)に当たることとする。
障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
重要なのは「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態」と定義されている点。次に、病名としての性同一性障害の公的な定義に当たりたい。
性別といえば、男性か女性の2種類に分かれると多くの人たちは単純に考えます。しかし、性別には生物学的な性別(sex)と、自分の性別をどのように意識するのかという2つの側面があります。性別の自己意識あるいは自己認知をジェンダー・アイデンティティ(gender identity)といいます。多くの場合は生物学的性別と自らの性別に対する認知であるジェンダー・アイデンティティは一致しているため、性別にこのような2つの側面があることには気づきません。しかし、一部の人ではこの両者が一致しない場合があるのです。そのような場合を「性同一性障害」といいます。つまり、性同一性障害とは、「生物学的性別(sex)と性別に対する自己意識あるいは自己認知(gender identity)が一致しない状態である」と、定義することができます。
(引用元:厚生労働省 みんなのメンタルヘルス - 性同一性障害)
この定義が厚生労働省の見解なのか日本精神神経学会の助言を受けての見解なのかはわからないが、この定義は大きな誤りを含んでいる。もしこの定義を是とするならば、全てのトランスジェンダーを「障害」として位置付けてしまうことになる。障害者基本法における「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態」という要件がすっぽり抜け、あまりに杜撰に「性同一性障害」を定義している。
実際に厚生労働省がこういった定義をしたのかあるいは委託先相談先の人間がそうしたのかは先述した通りわからない。しかし、省庁のページにこのような飛躍した正確でない定義を載せるのはいただけない。
実は障害者基本法とは別に性同一性障がい者に関する法令は存在しており、そちらでは性同一性障害を以下のように定義している。
第二条 この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。(性別の取扱いの変更の審判)
(引用元:性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律)
僕としてはこちらの定義の方がより正確なものであると感じる。「自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者」という本人の意思を加味している点が先述の厚生労働省による定義との大きな違いである。即ち、トランスジェンダーであることと性同一性障害であることは必ずしも同一ではない、ということが読み取れるのだ。僕は正にそこに引っかかっている。トランスジェンダーは性(及び性自認)の多様性であり、それを認めようという話をしているのだから、病名としての性同一性障害と同一視することは何かひどくおかしな事のように感じられる。
決してトランスジェンダーの方を擁護して性同一性障害の方を誹謗しようというねらいや、またその逆もない。僕は概念的に別のものであるべき二つのものを同一として捉えていることについて、単純に引っかかりを感じているのである。
さらに言えば、性同一性障害を「障害」と呼ぶことにも違和感を覚えている。先に挙げた性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律や他の法律において、性別適合手術を行うために必要な医学的(病理学的)診断名として性同一性障害という名前を使っていることは理解できる。また、社会福祉の観点において障がいというくくりを与えることの利益も多少なれ想像できる。他の精神障がい、知的障がい、身体障がいと同様の扱い(あるいは内包)をすることでそれらに対する福祉と同様の福祉が提供できるという、福祉の拡張性を重視した論理からこのような状況になっているのだろう。
性同一性障害に関して思うところはたくさんあり、この場では語りつくせない。よってここではブルーボーイ事件を紹介し当領域における日本の司法の致命的な失敗、その後にわたる法整備の遅れの文脈を指摘するにとどめる。
加えて、アメリカ精神医学会による診断分類(DSM)ではDSM-5において「性同一性障害」という表現を「性別違和」という表現に修正したことにも触れておきたい。先述したように、現代日本の法律や医療制度において障害か障害でないかという区別が必要であるという文脈には一定の理解ができるし、障害という言葉用いている法令や日本精神神経学会(だけなのかは分からないが)を責めようというわけではない。しかしやはり(アメリカを世界の基準とすることの是非は置いておいて)世界的、時代的な潮流と鑑みるに障害という表現は改善の余地があるように感じられる。これは他の障がいにおいても同様である。
そもそも「マイノリティ」というのは本当なのか?
LGBTという言葉が全てのセクシャルマイノリティを表現出来ているわけではないということは先述した。では他にどの様なものがあるか例に挙げると、アセクシャル、ノンセクシャル、パンセクシャルなどがある。性自認や性的指向はデジタルな区分でなくグラデーションのように多様であるから、全てのマイノリティに名前をつけることは非常に難しい。そして名前をつける行為自体について、僕は文頭で表明したように反対の立場をとる。しかし今回は論理展開の都合上パンセクシャルに注目してもらいたい。
パンセクシャルは全性愛と訳されることもあるが、ここでは当事者であると自認されている方が「しっくりきた」と仰っている定義を挙げる。
引用元:パンセクシャルとバイセクシャルの違いをパンセクシャル当事者が語ってみた|LGBTメディア|Rainbow Life
しばしばB、バイセクシャルと混同されるパンセクシャルだが、「そもそも性別を気にしない」という点がバイセクシャルとの違いだと言える。
上記記事にも同様の事が書いてあり非常に共感を覚えたのだが、僕はこの定義を初めて見た時、今のパートナーが性適合手術を受けたいと言った時のことを想像した。パートナーの性的指向は引き続き僕の性に合致するとして、僕は性を訂正したパートナーとどう付き合っていくのだろうか。そのことを原因に離れるのかどうか。この問いはあまりに本質的であり、僕が「マイノリティ」という言葉に疑いを持つようになった理由である。
人によって違いはあるが、ホルモン注射による性適合(身体的な性の特徴を得る)過程には3〜4年の歳月がかかると当事者の方がおっしゃっていた。即効性のあるものではなく、徐々に移り変わっていくのだという。これが正しいとすると、もしパートナーが性適合をするとしても、直ちにその変化か目に見える形で現るわけではないということになる。
ならば、その時点ですぐさま問題となるのは将来の話のみである。当然のことながら、理想とする将来像、譲れないパートナー選びの基準やそれ自体の有無は人によって違う。この時生まれる判断軸を想像するに、大きくは六つ程の問いが生まれるだろう。
第一に、子供を残せるか残せないか。
第二に、同性の特徴(性質)を持つ人と生きていくことに自身の中で抵抗があるかないか。
第三に、社会的性別役割や性における封建的規範をパートナーに期待するかしないか。
第四に、世間における見え方を受容できるかできないか。
第五に、性が訂正されても同一の人間であると思えるか思えないか。
第六に、全てを差し置いて共に生きたいと思うか思わないか。根源的かつロマンティックな問いである。上記五つの問いは全て、結局のところこの問いに回帰する。
言うまでもなくこの段階で別々の道を歩むことを選択する人は当然いるだろう。そういった人を責めも擁護もするつもりはない。しかし、それが多数派であると断ずることについてはあまりに早計で、無根拠であると僕は考える。
加えて、パートナーの身体的性が訂正されていく過程を想像する。日々変化(修正でも訂正でも適合でもよい)していくパートナーを見て、僕は何を思うだろう。例えば体重の増減で考えてみよう。パートナーが少しずつ体重を増していったとして、その変化に強烈な違和感を覚えることは果たしてあるだろうか。僕の経験的範疇において、そんなことはないと断じよう。それと同様に、パートナーの身体的精神的性質が他の性へと転換されていくことで起こる関係の変化は、あるとしても緩やかかつ些細なことのように思える。それは果たして年齢を重ね考え方や価値観が変化していくことと、どれほどの違いがあるのだろう。そして、パートナー自身が性適合していく自身を喜んでいる姿、言い換えれば、願いを叶え幸せを得ていくパートナーを否定的なまなざしで捉えることができる人間はどれほどいるのだろう。
先ほどの六つの問いに、一つ一つ僕なりの答えを出していくとしよう。
- 子供を残せるか残せないかは僕にとってパートナーの判断基準にはなり得ない。
- 同性の特徴を持つ人と生きていけるかどうかは、その状況にならなければわからない。
- 社会的性別役割やその規範などそもそも僕の中には存在しない。
- 世間というものに恭順して生きたことはない。
- 性が訂正されても同一人物は同一人物である。向精神薬や抗不安薬によって気分を調整したとしても、僕は僕であると自認できることからそう言い切れる。
- そもそも上記五つの問いは僕にとって問題たり得ない。そして、全てを差し置いてでも共に生きたい。少なくとも今は現在のパートナーについてそう考えている。
また、僕はパートナーの喜びを共に喜べるような人間でありたいと願う。
よって、僕は自身についてパンセクシャルになり得ると結論した。この投稿をするにあたって、念のためパートナーに確認した。彼女は現在身体的性も性自認も女性であり、性的指向は男性であるそうだ。僕はそのことに少しの安堵感も覚えなかったことから、上記結論及びその論理強度に感情的強度を付与したことを記しておく。
では、僕のような人間が特殊なケースなのかどうか。統計的に証明しようとしても、この件に関しては慎重な自問自答と具体的な想像を経た人からデータを取らなければ意味がなく、困難である。その上、もし僕を特殊だとする立場の人がいたとして、その方がそう思えるパートナーを獲得していないからそう考えた可能性もある。未だ残る社会通念上の誤解や印象により僕のような人間に忌避感を持つ人でも、社会が変わればその忌避感が失われる可能性は大いにある。また、動物的本能が種を残そうとするのだから同性愛や子孫を残せない性的指向はやはり不自然だという論もあるだろう。僕の不勉強故に生物学やその類の学問のことはわからない。もしかすると生物学的にはそうなのかもしれない。しかし高次脳がこれほど発達した人類が生み出した社会および文化において、セクシャルマイノリティが多様性として受け入れられようとしている今、そのような本能がどれほど人間に対し威力を持っているのか僕は疑問に思う。
結論
つまり、誰もがセクシャルマイノリティになり得る可能性を持っており、であるならばセクシャルマイノリティはもはやマイノリティとは言えないのではないかというのが僕の主張である。
尚、本記事において様々な表現を用いましたが、特定の性、障がいをもつ方、また持たない個人を差別、攻撃する意図は全く御座いません。
三浦しをんさんが女性だと知って僕はショックを受けた

- 作者:しをん, 三浦
- 発売日: 2011/02/26
- メディア: 文庫
何がショックだったかって、僕が三浦しをんさんを男性だと思ってしまっていたこと、つまりは未だ無意識の内に性差別的観点を蔓延らせていること、そしてそれを少しも自覚していなかった自らの愚かさだ。
彼女の本は「きみはポラリス」、「舟を編む」、「私が語り始めた彼は」などからはじまりそれなりに読んでいたつもりだった。凄まじい程に巧妙で的確、そして美しい文章を書く人だなあとずっと思っていた。二、三頁に一文は必ず「言葉でこんなことを描ける人間がいるのか」という驚きと確かな敗北感を覚える文章がある。それくらい三浦しをんさんは素晴らしい作家だ。
恐らく、その敗北感が僕を錯覚させたのだと思う。こんなに凄い文章を書く人はどんな人だろう、内に秘めた暗さをこんなにも明らかに隠せる人はどんな人なのだろう。そして、「しをん」という筆名を選んだ人はどんな人なのだろうか。僕の想像は、気が付けば一人の若い天才的なセンスを持つ男性を作り上げていた。これまでの人生から、友人から家族から、大学から社会から、僕は性に対する偏見の理不尽さ、罪深さをたくさん学んできたはずなのに、なんとなくのイメージで三浦しをんさんは男性だと思ってしまっていた。
もしこの誤解が彼女の文章に対する敗北感に由来するものだとすれば、口では男女に優劣など一切ないと言い、頭と心もそれに同意していたつもりでも、それは表面上のポーズに過ぎなかったのかもしれない。つまり、僕は心や頭の奥底で女性蔑視、性差別をしてしまっていたのではないか。そうは思いたくないが、そうだとしたら僕は僕が軽蔑する人間達と同じになってしまう。
僕が最初に『秘密の花園』を手にしていればこの勘違いは起こらなかったかもしれない。秘密の花園は非常に女性らしい繊細なお話だ。女子校に通う少女をこれほどの浮遊感と開放感に満ちた文章で包みこむ作品は男性には作れないのではないかと気付けたかもしれない。
しかしこれまで読んできた彼女の作品は、僕を完璧に騙した。彼女の本を読めば読むほど、この本の著者は僕のいる世界とは隔絶された次元からこの世界を覗いているのではないかと思わせられる。精密で大胆な描写、その確かな実力を敢えて見せつけるでもなく淡々と想像を絶する着眼点で人の想いを世界の動きを表現する胆力。どれを取ってもこの人は天才だ。
そして何より、彼女は人の感情を論理的に描写できる数少ない作家だ。多くの作家は登場人物の激しい感情を描写する際に少し突拍子にも思える表現やセリフを言わせる。それは敢えて動的なリズムを文章に取り入れるという目的のものもあれば、作者の力量不足で止むを得ずそうなってしまっていることもある。
しかし、彼女の感情描写は驚く程滑らかに行われる。人の感情の揺蕩いの殆どは、突飛に見えどもそれなりの論理に基づいた波形の道程に過ぎない。桜が初春に蕾を蓄えやがて春には満開に、そして残花に侘しさを託して散りゆくが如く、人の感情の開花とはその足踏みから残心まで、前兆と余韻を持つものなのだ。感情、情景の機微をこれ程までになめらかに、鮮やかに、そして論理的に描ける作家はそうはいない。
その論理性にこそ騙された。彼女の描く論理の繊細さはややもすれば神経質にも思える類のものだ。神経質といえば男性、という僕の中に蔓延る一種の性差別が彼女に対する決めつけを起こした。性差別、ジェンダー差別、人種差別などクソ喰らえと公言している僕ですら、区別としての男女比較の範疇を超えた誤認をしていたというわけだ。
僕はショックだ。論理的で美しく整然とした文章を書く女性がいて何がおかしいというのだ。クソ食らうべきなのは僕の方だ。ちくしょう、差別的思想なんて捨て去ったと思ったのに社会は僕の無意識の部分にまで差別を植え付けている。跳ね除けてきた自信はあったのに、まったく敗北した。いつかこんな社会壊してやる
悪気はなくとも、言葉は人を傷つける。
コミュニケーションというものは難しい。適切な言葉を選んで発することも難しい上に、相手の話を聴きしっかりと理解することもまた更に難しい。
男性の友人と飲んでいたとき、会計を済ませた僕らを可愛らしい店員さんがエレベーターまで送ってくれたことがあった。
「お仕事お疲れ様です。明日からも頑張って下さい、またお待ちしております。」
柔らかな笑顔で気持ちよく僕らを送り出してくれた店員さんに対し、友人はこんな言葉をかけた。
お姉さん、もう少しお仕事頑張って下さい。
店員さんはその言葉を聞いてキョトンとしていた。友人も店員さんの反応が予想外であったのか、一緒になってキョトンとしていた。ほんの少しの時間が過ぎて、可愛らしい店員さんの笑顔が引き攣り始めたその時、僕はこのコミュニケーション齟齬の全てを理解した。
僕の友人は、店員さんに対して「お前は仕事が出来ていないからもっと頑張れ」と叱責したのではなく、「閉店まであと少しの時間ありますが、お姉さんもそれまで頑張って下さい」とエールを送りたかったのだ。
しかし店員さんはそれを叱責だと受け取り、さっきまで上機嫌そうにしていた客が急にマサカリを投げつけてきたことに困惑する。友人は友人で丁寧に相手を労ったはずなのに、微妙な間を作り出してしまったり笑顔を引き攣らせた理由が分からず困惑する。
僕は慌ててディスコミュニケーションの構造を二人に説明した。店員さんは「なるほど!怒られたのかと思いました。」と笑顔を取り戻し、友人は「ありがとう、危うくサイコパスかなにかに見られるところだった」と胸を撫で下ろしたようだった。
昨今ではメールやチャット等、文面でのコミュニケーションをとることは誰もがやっていることであると思う。リモートで働く人も増えているし、そもそも対面でコミュニケーションを取ることをコストとして捉える風潮もある。しかし、情報量の多い対面のコミュニケーションでさえ先述した友人と店員さんのようなディスコミュニケーションは生まれてしまうのだから、文面ではもっと頻繁に、より悲惨なことが起きていると推察するのは自然なことだろう。なればこそ、我々は特に文面上のコミュニケーションを行う場合は普段より互いを気遣うべきだ。
言葉の重み
僕は基本的に大切な友人や恋人とはあまりラインやメールでのやり取りは行わないようにしている。表情の作り方、声のトーン、話すスピード、イントネーション、善意/悪意の有無、感情の強さ。これらの情報が付与されないコミュニケーションを苦手に思っている。恐れていると言ってもいい。
僕の言葉は率直すぎるというか、短慮になってしまうことが多いようで、気付かぬ内に人を傷つけてしまうことが今まで度々あった。基本的に人に嫌われたくない人間であるはずなのに、人を傷つけてしまっていて、それに気づくことさえ出来ていなかった。僕の言葉で傷ついた人がいるという事実を人伝に聞いた時なんかは結構ショックを受けた。それはもう、少なくとも二、三日引きずって落ち込むくらいに。
そういった経験から、僕は状況に合わせて慎重に言葉と態度を伝えることを心がけるようになった。当然今それが完璧に出来ている訳ではないし、考えるのが面倒になって短慮な言葉を発してしまうことも多々あるが、なるべく不本意な状況を作らないよう気をつけている。
それでも、やっぱりコミュニケーションは難しいと感じる。例え僕が本当に慎重に言葉を選んで大切なことを伝えようとしたとしても、相手がそれをどう取るかは結局のところわからない。僕なりに心を込めたメッセージを発したとしても、その重みや思いが相手にうまく伝わらないことはある。それは相手と自分の関係性の影響もあるし、自分の普段の立ち居振る舞いがそうさせているのかもしれない。
同じ言葉でも、誰にそれを言われるかで受け取り方や感じる重みは違う。僕の言葉や考え、アドバイスなんかを「そうだよね」と納得してくれたとしても、それが表面上の納得に過ぎず、「こうしたらいいかもしれないよ」と伝えたことが実行されないなんてよくあることだ。
よくあることなんだけれども、そういう時、僕は悔しさというか、不甲斐なさのようなものを強く感じる。うまく伝えることが出来なかった、僕では役に立てなかった、そんな思いが心の奥底にポツンと種のように残り、いつかパキパキと音を立てて発芽してしまうのではないかというぼんやりとした不安を覚える。でも、それってしょうがないことなんだと思う。
逆に、僕がそれほど重みを持たせずに発した言葉が相手には重く伝わってしまうこともある。それがひどく相手を傷つけることも。僕の軽い言葉で誰かが傷つくということは、つまりその誰かは僕の言葉を真摯に聴いてくれようとしていたということだ。そんなに僕を大切に思ってくれている人を傷つけてしまうなんて、本当に怖いことだ。傷つけるつもりはなくとも、言葉は時に相当な威力を持ってしまう。その刃は相手にも自分にも向けられる。
元気のない時期、単刀直入に言えば鬱病を患っていた時期に、僕はたくさんの人からアドバイスや心配の言葉をもらった。多くの人が、おそらく僕のためを思って本心から心配してアドバイスをくれていた。けれども、僕がその重さをしっかりと理解できていたかと言われると、わからない。もしかすると、僕に優しくしてくれた人々も、僕が感じるような悔しさを感じてしまっていたのかもしれない。僕が、そう感じさせてしまったのかもしれない。それを申し訳なく思う一方で、僕は僕が慎重に選んだ言葉の重みを理解して欲しいと願ってしまうエゴも捨てきれない。
そんなのは結局お互い様だ、と簡単に言ってしまうことはしたくない。簡単な話ではない気がする。物質世界において、言葉に重さなんてものはないのだけれど、でも、言葉の重みというものは確かに存在する。この話を難しくしているのは、それを計る尺度が人それぞれ違って、またその尺度自体も状況や相手、感情や思考によって大きく変化をすることだ。だからこそ、言葉の重さがもたらす問題と折り合いをつけるのはとても難しい。自身を省みて、相手にエゴを押し付けないようにしなければならない。そんなことが出来る清い人はなかなかいない。
そんな人はなかなかいない。そんなことはなかなかできない。けれども、僕ら人間はコミュニケーションを取らずにはいられない。面倒で、難しいことで、厄介なことで、大変なことなんだけれども、やっていかなければならないことなんだ。それがとても、僕には難しいよ。
本を読めるかどうか、という人生の指標

- 作者:窪 美澄
- 発売日: 2017/05/25
- メディア: 文庫
最近は、窪美澄と連城三紀彦の小説を読み漁っている。通勤時間には小説を、仕事中は仕事を早く終わらせて技術書や論文を、それぞれ時間を割り振って週に4〜5冊のペースで本を読んでいる。連城三紀彦『恋文』、窪美澄の『水やりはいつも深夜だけど』この二冊は限りなく完璧に近い小説だった。間違いなくオススメできる。僕の友人であったり、僕が書く文章を少しでも気に入ってくれている人がいるのならば、絶対に読んだ方がいいと断言できる小説だ。
そんなペースで本や論文を読む僕を見て、彼女は「活字に飢えてるね。もはや猟奇的だよ」と言う。確かにその通りだ。僕はストレスが溜まると狂ったように本や映画、漫画やアニメを消化し何かを補給しようとする。それは彼女の言う通り、まさしく猟奇的な程の衝動で、飢えという表現も相応しい。
きっと、現実逃避なんだ。何か活字や物語を消化して自分の中に取り込まないとこの物語性のない平坦な毎日に埋もれてしまうような、そんな焦燥感を僕は覚えている。意外にも、挫けそうになったり、挫けてしまった時にはそのような飢えは襲ってこない。自分でもそんなものを未だ残していたことに驚いてしまうんだけれど、辛い時や疲れた時にだけやたらと責任感や使命感のようなものが出張ってきて、辛さや疲れから離れることを許してくれない。僕はどうやら、辛くなる前や疲れていない時、つまり余裕が少しでもある内に出来るだけ現実逃避をするようにしているらしい。
転職面談の際「一番最近に読んだ本は何ですか」と問われ、僕は「銀河鉄道の夜です」と答えた。それが原因かどうかはわからないが、その会社の選考は落ちた。エンジニアとしては、技術書や自己啓発本を挙げるのが正解だったと思うし、一応の補足として技術書のタイトルもいくつか挙げた。相応しくない答えだったとは理解している。しかし、当時僕が最後に読了したのは宮沢賢治の銀河鉄道の夜であったし、そう告げることは僕にとって、企業に対する宣戦布告の意思表示でもあったのだ。
僕は、本を読めない程忙しかったり追い詰められたりする会社には絶対に入らない。今の会社は業務の役に立つ技術書ならば業務時間に読んでも構わないし、コアタイム外の時間に何をしようが成果さえ出せば構わない、なんならコアタイムの間にどこにいようが構わない、喫煙所でタバコを吸いながら作業をしてもいいとさえ言ってくれている。僕の上司や僕の同僚達は、僕にとってこの環境こそが給与や待遇よりもずっと価値のあるものであることをきっと知らない。何なら今の僕にとって、仕事先として重要なのは本を読めるかどうかの一点のみと言ってもいい。たとえ給与が多少下がったとして、自由に本が読める時間が増えるならば一向に構わない。それはまさしく僕のエゴであり、読書をすることでアウトプットの質が高まるなどとは決して約束出来ない。
このような環境が与えられ、僕がそれを本当に実行し始めたのはごく最近のことだ。別にそれでいいよ、と言われてはいたがいざ実行に移すとなるとどうせ批判が飛んでくるのだろうと悲観的に考えていた。だからこそ最近まで本気で転職を考えていたのだが、実際に業務時間内に本を読み、使える知識があればそれを共有するということをしていたら、その共有が批判されるどころか褒められるようになってきた。具体的にはこのブログに投稿した記事(下掲)を共有したり、すごいエンジニアの安井さんという方が発案されていたスクラム体験ワークショップ(下掲)をお昼休みに開催したりteam geekの宣伝をしている内に、なんとなくチームが上手く回り始めるようになってきた。そしてそんなことをしていたら会社全体に僕の存在が段々と認知されるようになってきた。
僕がソフトウェア開発について学んでいること - ここはクソみたいなインターネッツですね
まあ「あいつは何をやってるんだ?」というまなざしも多少はあるんだろうけれど、今のところ褒められることの方が多いので最早僕が今の会社を辞める理由も無くなった。こうなると転職活動もただの時間の浪費でしかなくなるので一旦ストップすることにした。
本を好きな時に読めて、またそれが認められるかどうか。僕はクオリティオブライフの重要な柱として、この指標を大切にしていきたい。そしてまた、そうしたことで気持ちに余裕を作り、大切な人との時間を優しさに満ちたものに保ちたいと、心から思う。
バグって言うな問題は構造の問題なんじゃないか
先日から友人のエンジニア達と、はてな界隈でバズっていた記事について話している。
提案:エンジニアに気軽に「バグ」というのはやめませんか? - worker experienceの日記
バズっていた記事とは上記のもので、簡単に言うと「エンジニアに"バグ"と気軽に言わないでほしい」という提案を投げかける内容だ。
ある友人は上記記事を「エンジニアのエゴだ」と断じ、ある友人は「バグって言われるとウッとなるから共感出来る」と言う。僕はどちらの気持ちもわかる。
たしかに、ユーザーや顧客からすれば正しくないデータを表示したり望んでいない挙動をするプログラムにはバグがあると思って当然である。それが仕様だとしても、そんなことはユーザーにとっては知らないし関係のないことだ。
要求の履き違えであったりビジネス要件認識のズレであったり仕様通りであったり仕様漏れであったり普通にバグであったり、システムがユーザーの思った通りに動かない原因は色々ある。でも、原因なんてことはユーザーには関係のないことなのだ。思った通りのものが得られない。それが何より重要なことなのだ。思った通りのものが得られないシステムに対し、それをバグや不具合と呼んでしまうことに罪はない。ほかに相応しい言葉を知らないのだし、それこそシステム面か仕様に踏み込める人間でないとそれがバグなのかどうかなんて分からないのだ。システムをわからない人に仕様を調べて指摘しろというのはエンジニアのエゴであるし、単に"バグ"という言葉を嫌うのならばそれこそ"ドラゴン"と呼ばせてみればいい。結局ドラゴン=バグなのだから、呼び方を変えたところで根本的な問題は解決などしないと思う。
しかし一方で、バグという言葉がいかにエンジニアを傷つけるかということも僕はよく分かる。痛いほど分かる。
バグを起こしたエンジニアのリアルな感情の流れ - ここはクソみたいなインターネッツですね
バグじゃないものをバグだと呼ばれることで、エンジニアは不要なストレスを感じる。またバグという言葉が横行することで本当に直すべきバグが隠れてしまうという話も納得がいく。どちらの気持ちもわかるエンジニアとしては、この問題の根本的な構造を改めて解きほぐしていきたい。
友人達との結論
面白いのは、何度か違う場所で違うエンジニアとこの話をしたけれど、出てきた結論が同じであったという点だ。
結局「エンジニアとその他」という認識か、あるいはそう認識させてしまう構造の問題じゃない?
僕らはいつもこの結論に至った。
例えばシステムとドメイン領域両方の理解をしたディレクター、あるいはプロダクトオーナーのような人間が居れば、エンジニアに"バグ"という言葉が伝わる前に一度咀嚼してもらえるはずだ。更に言えば、例えそういった役職がなくともビジネスサイドの人間とシステムサイドの人間にしっかりとしたチーム意識があれば、エンジニアではない人間もプロダクトに対してプライドや"自分ごと"意識が生まれているはずである。その場合「バグでないものをバグと呼ばれてムッとする」のはエンジニアだけではないのが自然だ。ビジネスサイドの人間とシステムサイドの人間がしっかりとパートナーシップを結べていないからこそ、此岸と彼岸というようにエンジニアとそれ以外を断ずることが出来てしまう。一つのプロダクトに対し、ビジネスとシステム双方を織り交ぜた強いチームが存在していれば、そもそも「エンジニアにバグと言うのをやめてほしい」というような話は出てこないはずなのだ。ネガティブに言っても「プロダクトのことをよく分かっていないのにバグと言わないでほしい」となるか、普通ならば「このプロダクトにはバグだと思われてしまう問題があるんだな」というポジティブな受け取り方になるはずなのだ。
こうした論理から、僕と友人のエンジニア達は、結局この問題は認識か構造の問題であると結論した。
僕の感想
けれども実際問題、そんなに強いチームが出来ていることなど稀だし、バグだー不具合だーと直接エンジニアに言ってくる人は少なくない。でもやはり僕は、それはその人のリテラシーや気遣いの不足が悪いというわけではなくて、そう思わせてしまうシステムに原因がある場合がほとんどだと思う。そしてシステムのことはシステムの人間にしか分からないこともあるのだから、柔らかく「どんなバグですかー?」とこちらから歩み寄る姿勢こそが必要なんだと思う。
殆どの人はエンジニアを傷付けるつもりでバグという言葉を使っているわけではないのだし、エンジニアがバグという言葉で傷付くかどうかを想像しろなんて酷だ。逆にわからないものをバグと呼んでいるんだという想像は容易なのだから、まずは余裕を持てる方が歩み寄り、最終的には互いの歩み寄りが行える構造を目指すべきだ。
全人類がTeam Geekを読めばいいのに

Team Geek ―Googleのギークたちはいかにしてチームを作るのか
- 作者:Brian W. Fitzpatrick,Ben Collins-Sussman
- 発売日: 2013/07/20
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
僕はエンジニア二年目だか三年目だかの時に、先輩に勧められて一度この本を読んだことがある。その後しばらくして僕はリーダーと呼ばれるような立場となり、チーム開発や自分の仕事、世界そのものと自分自身をとても嫌いになるようなひどい経験をした。僕は鬱を理由にそれらのことから逃げ出して、逃げられるだけ逃げようと決めた。社会から、自分自身から遠ざかってしまいたい。当時はただその一心だった。そんな僕は、なんの奇縁か今再び似たような業界で、まさしく嫌悪していたはずのチーム開発をしている。
僕がこの本を改めて今読んだ理由は、チーム開発に対するトラウマを克服するため、また何故僕はあの時失敗し身も心もバラバラに散ってしまったのか、それを知りたかったからだ。そして僕は今それ以上のことを知った。この本が最高の本だということ。そして、死ぬほど苦しんだあの時期にこそ読むべき本だったということ。
当時は、一緒に働く人を信頼し、尊敬し、そして自身は謙虚であるべきだというこの本の願いや、その重要性を真の意味では理解できていなかった。断言する。Team Geekは単なる自己啓発本などではなく、地獄とクソをミックスして焼き上げたようなこの社会から自身を守り、また少しでもその地獄を歩きやすくする方法をまとめたガイドブックのようなものだ。僕はそれを知らずに、足裏を糜爛させながらトボトボと焼けた地面を歩いていた。少しすると当然脚は使い物にならなくなって、四肢を使い果たした頃にはもう手遅れだった。身体も心も社会や人間との摩擦で削られて、僕は僕の半分くらいを失ってしまっていた。
僕は元来、自己啓発本と呼ばれるような本はあまり好きではない。どうしても偉そうに講釈を垂れられている気がしてしまって、反発してしまう。それこそ流行の自己啓発本をいくらか読んで出て来た感想は「わかってるよ、うるせえな」という程度のものだった。それは今でも変わらない。偉そうに自己啓発本を読めと言ってくる人間も大抵嫌いだ。そういう奴らが彼らのいう大切ないくつかの習慣を本当に習慣付けているところを見たことはないし、何かを引き寄せているところも見たことはない。彼らは嫌われる勇気を持つのではなく、もともと自分のことしか考えていないから嫌われてもなんとも思わない。これからの正義の話をするのではなく、自分自身が正義であることを主張する。ああ、悲しい哉。本自体は偉大な本であっても、君はその本ではないし、その本を書いた人間でもない。その本を君から勧められたとして、何故僕が読む気になると思うのか。何故そんなにも無自覚に正しさを押し付けられるのか。というか大体あいつらは、一体いくつの習慣を身につければ気が済むんだ。何か自分が成長しているっぽいエビデンスとして自己啓発本を読んでいることなんて、君が無自覚だとしても、みんなが気付いているよ。それらしいものを消費できれば、もはやなんでもいいのだろう。
話が逸れた。信頼と尊敬の重要性を語るこの本を紹介するにはふさわしくない吐露だった。ごめんなさい。
ではなぜ僕がこのTeam Geekについてだけは自己啓発本ではなく(しつこいようだが地獄とクソとゴミと嘘を捏ねて叩いて整形せず焼き上げたようなこの恨めしい社会の)ガイドブックだと称し、わざわざ日記まで書いているのか。それは偏にこの本が人々に寄り添うものだからだ。上からものを言うでもなく、正しさを押し付けることもない。この本に書いてあることは、著者らの痛み、こうしたらなんとなく上手くいったという経験、痛みを繰り返さないように気をつけていること。基本的にこの三つに終始する。それを主張や説教などという強いスタンスに乗せるのではなく、読者に対する親しみを込めた語りかけという優しさに乗せている。寄り添うというのはこういうことだ。不思議な世界に連れて行ってくれる本や、ドラマティックな日常に巻き込んでくれるような本、正しい道を歩ませようとする本、反骨精神を呼び起こしてくれる本。たくさんの本を読んだけれど、僕はこんなにも友人と話しているような気分にさせてくれる本に出会ったことはない。
この本が多くの人に読まれ、皆が皆生きやすい社会を作る一員となってくれると僕は嬉しい。そして僕も、その社会の中で車輪となるのであれば本望だ。